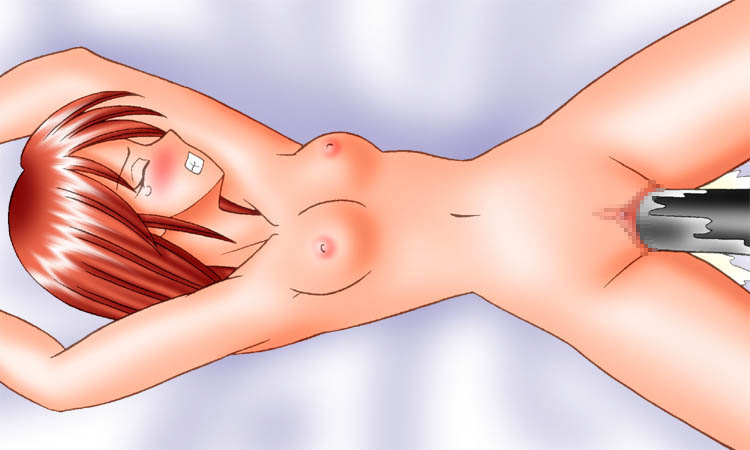Mr永峰様作
格闘凌辱ファンタジー<カヴァルナの姫> 亡国の王女の悲劇 第3部
第1話 プリセア姫は変態ペルツに体を拘束される
カヴァルナ国は小さいながらも商業で栄えていた。
洗練された文化が花開き、多くの国と友好的な関係を築いていた。
時たま戦争に巻きこまれることはあっても、数こそ少なくとも兵士は勇壮で祖国カヴァルナを侵略者からよく守ってきた。
そして、その戦陣にはいつも美しい戦う姫君プリセアの姿があった。
しかしその華やかな歴史も軍事大国ボルゴニアの伸長で終わりをむかえた。
数万の大軍に長く包囲されては、勇気も名望も何の役にも立たなかった。
多くの求婚者が競っていたプリセア姫は無頼漢のグロイス王子の手に落ち、二十二歳のお姫様にとって戦いの場は広々とした草原や野山から暗く忌まわしい敵の城のベッドに移った。
「触らないでっ!」
「うはは、これも王子様のご命令ですのでな。花嫁さまが夫となるおかたのことを忘れないようにという訳で。」
いやらしい猫なで声でイヤミを言うのはご存知、王子の御用商人のボン・ペルツである。
かたやプリセア姫はベッドに寝かされたまま身動き一つできないでいた。
頑丈な革手錠が彼女の両手と両足を捕らえ、華奢な体をむりやりXの形に引き伸ばしていた。
「これは、どういう訳ですっ!」
夕食のあと眠気がさしたところまでは憶えているのだが....。
きっと悪い薬を盛られたのだろう。
悔しさに歯ぎしりしても後の祭りだ。
こんな人生経験の浅い小娘を罠にかけるぐらいボン・ペルツにはお手のもの。
今夜の彼は、プリセアのまぶしい肢体を思うさまオモチャにしようとしていた。
「ほ、ほんとうにあの人が....こんな事を命じたのですかっ?」
グロイスに弄ばれるのも嫌だが、こんな変態中年に体を預けるのは考えただけで虫酸が走る。
「おやおや、お疑いとはあんまりだわい。良いですかな? お上品なプリセア様には想像できかねるかも知れませんが、実はこのペルツめは王子様のお手付きになる女をしっかり調教するのが主要なお勤めなのでしてな。ま、姫様がだだをこねている内は他のお嬢ちゃんがたに代役をお願いするしかありませんがね。」
とんでもない破廉恥な家来っぷりだ。
プリセアはあきれ過ぎて怒ることもできない。
でも人質になっているカヴァルナの娘たちを盾にとられては逆らえない。
「モナ、お召しものを脱がせてさしあげるんだ。」
部屋のすみから召使いのモナが進みでてくる。彼女もほとんど裸に近い淫らな恰好をさせられている。
「お願いモナ、止めて。止めさせて。」
「お許しください。姫様、わたし....どうしようもないんです。」
モナの手がプリセアのスカートをめくり上げると刺繍をほどこした豪華なシルクの腰布が表れる。
牝鹿のような高貴なふとももが滑らかに筋をうって白い布の下から伸びている。
プリセアは必死に足を閉じようとするのだけれど、足首だけでなく膝頭にまで付けられた革ベルトが丈夫なロープでもってベッドに結わえつけられている。
彼女にできることと言ったら無駄な抵抗をすることで逆に男のサディズムを煽るぐらいだ。
「モナぁ、やめて....」
恥ずかしさのあまりプリセアは目をつむった。
そんな哀れなようすにモナもいくらか躊躇したが、ボン・ペルツの指図には逆らえなかった。
ポルガという悪魔の薬のせいでモナはとっくに人間性を奪われた操り人形なのだ。
「姫様、おキレイです。」
モナは秘められた丘を包むシルクの上にそっと手を乗せる。
プリセアの体温を感じる。
それは心とはうらはらに高まってしまう女の官能だ。
「いやぁ....」
モナが腰にまわっているヒモを解いて引くと、小さな布地はするりと落ちて、生まれも育ちも関係なく女そのものな部分が光のもとに出る。
変態ペルツは手をたたいて喜ぶ。
「うほほほほ、下のほうも髪と同じみごとな栗毛ですな! 剃るのが惜しいぐらいですわい。」
その言葉がプリセアの頭をガンと打ちのめした。
「そ、剃るって! どういうことですっ?」
ベッドに拘束され、女として一番恥ずかしい所をあらわにされながら、プリセア姫は思わず声を荒げた。
しかし変態中年のボン・ペルツは落ち着いたものだ。
「剃るは剃るですよ。この私めの頭みたいに、姫様のそこんトコにもすっきりしていただこうという計らいですわい。」
「そんな....」
「神聖で偉大なるわがボルゴニア王国では、男は髭を伸ばす。女は下の毛を剃る。これで釣り合いがとれるわけです。役割分担というわけです。」
めちゃくちゃな理屈を言ってペルツが目配せすると、召使いのモナが洗面器とカミソリを持ってきた。
「お許しください。」
「ダメっ! それだけは許して! お願い、モナぁ!」
カミソリの刃がきらりと輝き、プリセアはぞっと青ざめた。
第2話 プリセア姫はモナに下の毛を剃られる
変態商人のボン・ペルツに指図され、召使いのモナはプリセア姫の大きく開いた足の間に座った。
革手錠で拘束されていてはプリセアにはなんの抵抗もできない。
「お動きにならないで。....ケガしますから。」
「そう、暴れてはなりませんぞ。ピンクのお肉がそげ落ちてしまいますわい。」
プリセアの歯ががちがちと鳴る。
処刑場で斧を見せつけられた死刑囚の気分だ。
モナはよく泡だったクリームを手のひらに掬って、主人のヘソの下へそっと乗せる。
反対の手で優しく子供の頭を撫でるみたいに女体の膨らみをさすって、これから剃ってしまう柔らかな毛に別れのあいさつをする。
冷えた鉄の刃が柔肌に触れた瞬間、プリセアの口から小さなうめきがもれた。
「ゆるして....」
これが見知らぬ他人なら、ただ憎むだけのこと。
でも長く仕えてくれたモナの手で辱めを受けるのは辛く惨めなものだ。
「姫さま、おゆるしください....」
モナもそう答える。
でも手のほうは容赦なく命じられた仕事を始める。
ぞりぞりと嫌な音がして、少女の日に生えてから一度も失われたことのないものが削ぎ取られていく。
長い時間のように思えた。
カミソリが撫でるたびにプリセア姫はひっ、ひっと情けない声をあげた。
まるで大事なところの毛と一緒にプライドの残りのひとかけらまで奪い取られるようだ。
「終わりました。」
モナの言葉にずきりと胸が痛む。
プリセアは顔を壁のほうに背けていた。
壁にはプリセアの姿を刺繍したタペストリーがかかっていた。
プリセアが二十歳になった時、今は亡き父のカヴァルナ王がプレゼントしてくれたものだ。
戦火にすすけ、焦げがつき、プリセアの像の股のところには裂け目がついていた。
絶望するしかない彼女の運命を示しているようだ。
「お綺麗ですわ。」
慰めるようにモナが言う。
湿らせた布でそっとぬぐうと、ふっと息をふきかける。
「はあああっ。」
思わずはしたない声をもらしてしまい、プリセアは慌てて口を閉じた。
そのようすをモナは愛しそうに見つめた。
(姫さま、もう....もう何も考えなくていいんです。)
考えたら辛くなる。
いっそ全てを諦めてしまえば、弱い女であることに流されてしまえば、そのほうが楽になれる。
モナは主人のふとももの間に顔を下ろすと自分の唇をプリセアの陰の唇に合わせた。
「駄目、ちょっと、モナ! いけない....、やっ!」
モナは言葉でなく舌で答える。
ぬるりと入ってくる感触にプリセアはたちまち切ない顔をする。
「止めなさい! や、止めてっ! そんなの....汚い。ああぅ!」
粘膜の間を舌が蠢くのと同時にウェーブのかかった黒髪がプリセアの内股をくすぐる。
身動きできない分、かえって体が敏感になっているようだ。
「やあああっ。あぅ、あああ....っくうう! うあああ....」
ペルツに見られているのも忘れてプリセア姫はあられもなく喘ぎだす。
初めて毛を剃られた恥丘は、モナの息や鼻先があたるたび何ともいえないくすぐったい快感を生むのだ。
「もう、しないでぇ....はあぅ! あっ、あっ! ああああぅ、駄目っ駄目ええぇっ!」
プリセアはぶるぶると腹筋を震わせた。
今夜最初の小さなオーガズムだ。
ご奉仕を続ける舌を熱い肉がきゅっと締めつける。
「やああああ....あ....ああ....あ....」
腰を左右にくねらせる。
下半身だけが勝手に喜んでいるようだ。
小さな絶頂が立て続けに襲う。
「あうっ! はうっ! うあああっ! いやああん! あうっ! はあぁ....」
やっとモナが舌を離す。
汗ではない液体がべっとりと内股を濡らしている。
「ひゃっはは、いけませんなあ! 一国の姫君ともあろうお人がこんなに下品なおつゆを滴らせてしまっちゃ。」
言われる通りなのが口惜しい。
プリセア姫は唇を噛んだ。
泣き出してしまいたいのに、まだ官能の余韻を味わおうとする自分の体が恨めしかった。
(お父様、お母様、私、汚れてしまいました。)
呆然となっている彼女の目の前に黒い棒きれがさし出される。
「ほれ、これに見覚えありませんかな?」
ボン・ペルツの声がいやらしく上ずった。
第3話 プリセア姫はペルツに無理矢理イかされる
「うっ....」
目の前につきつけられたものの醜さに、プリセアは思わず顔を背ける。
それは木でできた大きな男根だった。
「偉大なグロイス王子様のモノそっくりに作らせましたのじゃ。どうでしょう。この逞しい反りぐあい。」
「悪魔っ。」
この男の禿げ頭の中にはいくらでも悪知恵が詰まっているらしい。
相手が嫌がることを思いつく点は天才的だ。
プリセアがにらむのをよそに、ペルツはポケットから妙な液体の入ったガラスビンを取り出す。
とことん道具にこだわるやつだ。
「変なものは、つ....使わないで。」
「ふふん、何の薬か知りたそうですな? そのうち分かりますですよ。」
筆でもって木製の男根にそれを塗りつけていく。
職人みたいな手慣れたようす。
蜂蜜が混ぜてあるのか花の匂いがぷんとする。
「さあ、こいつで姫様の欲求不満を解消してさしあげますぞ。」
「触らないでっ、嫌っ! 汚らわしいっ!」
蔑まれれば蔑まれるほどペルツは嬉しそうだ。
高いプライドをぶち壊すのがこの男の目的。
プリセアの恥ずかしい部分をまじまじと見つめる。下着も剥がれ、陰毛まで剃られて露わになった肉の花びらめがけ、おぞましい道具を当てがった。
「グロイス様だと思って、ずっぽり飲みこんでくだされよ。すぐに気持ちよくなりますでな。」
「いやああああああっ!」
しかしプリセアの肉は意志に反して人工の男性器をずるずると受け入れていく。
棒に塗られた液体と、さっきまでの愛撫で湧いてしまった体液のせいだ。
でこぼこした表面が粘膜のヒダを滑る刺激に足の先までびりびりと痺れた。
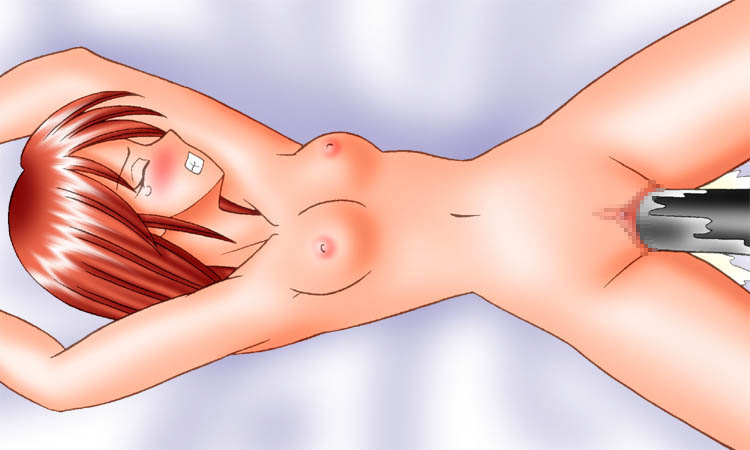
「やああぁ....うあ....あっ、くあっ、ううっ....」
(そんな、どうして? 気持ちいい....恥ずかしいのに。)
ペルツの醜い顔がいやらしく歪んで、高貴な姫の痴態を嘲り笑っている。
モナが悲しそうに見ている。
それが逆に彼女を悪夢のような快楽に追いこんでいく。
「うあ....はあっ、ああ、んああ....ふああっ、あああん....」
ゆっくりと動かされるのが辛い。
いっそ激しく突いてほしい。
でもそんなことは口が裂けても言えない。
「おっ? 滑りがよくなってきましたぞ。気持ちよいですかな?」
「くうっ....」
(駄目よ! 声出しちゃ駄目。しっかりしなくちゃ。こんな男を楽しませるなんて。)
でもそうやって必死に抵抗する気持ちも一突きごとに萎えてしまうそうだ。
下の毛を剃られてることで心身ともいつもより敏感になっている。
そのうえ、さっきの妙な薬の効果もあるのだろう。
体の芯がやけに熱い。
「気持ちよかったら思いっきり悶えてよいですぞ。遠慮はいりませんわい。」
だんだん責めが激しくなってくる。
とても我慢なんてできない。
「あぅ、ふあああぁ....うっ! くうう、やぁ....はあああうっ! うあああっ....」
自分の声の艶っぽさにプリセアはますます羞恥心をかき立てられた。
それに加えて、ぐちゃぐちゃと品の無い音がヘソの下から聞こえてくる。
耳をふさいでしまいたいけれど彼女の四肢はぴんと張った状態で動けない。
今のプリセアは伝説の戦う姫君などではない。
ただ男の色欲に弄ばれる生け贄なのだ。
「だめええ....そんな、あああっ! しないで....許して、許してええっ! あああああっ!」
あまりの快感にがたがたと体が震えてくる。こんなに感じてしまう自分の体が恐い。
「どうです。そろそろイキそうですかな? ペルツ様の技でイッちゃいますかな?」
屈辱的なことを言われて失いかけたプライドがまた戻ってくる。
プリセアは最後の強がりを言う。
「....だ、誰が....こ、こんなことで....くううあっ....」
「素直でありませんな。じゃ、モナ、あれをして差し上げなさい。」
いつの間にかモナの手には羽根ボウキが握られていた。
プリセアが「まさか」と思った通り、モナは羽根の柔らかい先端をプリセアの拘束された足の裏へさしむけた。
「ひゃあああああんっ!」
プリセアは子供のような悲鳴をあげた。
「姫様、びっくりしましたかな? これは一度やるとやみつきですぞ。」
モナは続けざまに右の足、左の足と羽根ボウキでくすぐる。
「きゃああうっ! だめっ! あん! やめてっ、やめて....きゃああああん!」
暴れるプリセア。
ベッドが地震のようにぐらぐらと揺れる。
凄まじいくすぐったさのために彼女の心を支えていた最後の抵抗心はたちまち崩れさった。
すると戒めを解かれた性感は一気に頂上へと駆け上がっていく。
「やめてええっ! 死んじゃうぅ、ひゃああああああうっ!」
「もっと! もっとだ!」
ボン・ペルツは媚肉に挿しこんでいる武器を乱暴にねじ回す。
固い男根型と柔らかい羽根の二段責めにプリセアは狂いそうだ。
動けない体で手足も引きちぎらんばかりに悶えまくる。
「いっちゃう! いくううっ! 止めてえーっ! いやあああああああーんっ!」
(わたし、壊れちゃう! 駄目になっちゃう! お願い、助けてえっ!)
子供のようで娼婦のような、そんな嬌態がペルツの変態性に拍車をかけた。
「イけえっ! もっとだぁ! ペルツ様の恐ろしさを思い知れ!」
「きゃああああうっ、きゃあんっ! ひゃうう....ひいっ、いくうううっ....あ....ふあああああっ! うああああああああーっ!」
プリセアが全身を弓なりに持ちあげて凄まじい痙攣で絶頂の合図をした途端、きれいに剃られた恥丘の下から透き通った飛沫がほとばしった。
その愛液の噴水は雨のようにモナの顔にふりかかり淫らな香りをたてた。
「あ....ふあ....」
プリセアの体はしばらく空中にあったが、やがてゆっくりとベッドに舞いおりた。
色っぽく汗ばんだ顔をペルツが覗きこむ。
「気を失っておいでかな? そんなに良かったか? よしよし。」
うっとりした顔で失神しているプリセア姫。
まだ木の男根をくわえこんだまま、どんな夢を見ているのだろう。
「姫様ぁ....おゆるしください....」
召使いのモナは泣きじゃくりながら姫君の胸に顔をうずめた。
そして小麦色のお尻をペルツのほうへ向けた。
「ご主人さま....可愛がってください。」
中年の脈うつ肉の杭が濡れきった穴に打ちこまれると、モナは泣きながら喜びの声をあげ始めた。
第4話 グロイス王子が戦地から帰ってくる
うだるような夏の暑さの中、ボルゴニアの首都の民はこぞって町の外に集められていた。
もうじき到着するグロイス王子を凱旋パレードで祝うためだ。
遠征軍の旗が数キロも向こうにひらめいて見えると、ラッパの合図に始まって城の塔の鐘がさかんに鳴らされる。
だが着飾った行列のなかにアルノス王の姿はない。
いよいよ近づくまでは宮殿の涼しい部屋で待っているわけだ。
「着いたようだな。」
「さようで。」
「大した戦闘もなかったそうだが。」
「さようで。」
「また女ばかり捕虜にしてきたのかな。」
「さようで…いえ、さあ…どうでしょう…」
失言に冷や汗を垂らす大臣をじろりと見ると、王は宝石や金細工で豪華なぶんだけ重い冠を白髪まじりの頭にのせた。
召使いがマントを持ってくる。
暑苦しいが仕方がない。
正式な場では王様は王様らしくしなくてはいけないのだ。
初老の父親がガマンしているからには息子は当たり前。
グロイス王子も鎧の上に毛皮の縁のついたマントをかけて馬車の上に仁王立ちしている。
家来が日傘を差しかけているが、地面の照り返しが強いのであまり意味がない。
「これだから儀式とかしきたりってやつは好かんのだ。」
「ま、ま、冷たい物を用意しておりますから。」
一足先に出迎えた御用商人のボン・ペルツがそういって慰める。
町の門まではまだ一時間ほどかかりそうだ。
プリセア姫は召使いの女たちの手で、夏用のドレスを着付けられていた。
水色で見た目にも涼しげで、しかもあちこちレースのおかげで風通しがよい。
「どう? 私の仕立て屋に特別にあつらえさせたのよ。」
「ありがとうございます。」
いつわりのない感謝でプリセアが頭を下げると、相手は赤い髪を揺らして笑った。
義姉になるパガレアだ。
始めは冷たい人かと思っていたが、最近では何かと女ならではの心配りをしてくれる。
本人の話を信じれば、乱暴者の弟グロイスのかわりに面倒を見るよう王様に言われているそうだ。
「よくお似合いよ。ジェロー、お前もそう思うでしょ。」
「はい。素敵でございます。」
遅れて入ってきた騎士のジェローが貴公子のようにほほ笑みかける。
プリセアはつい赤くなってしまう顔を隠すように窓の外を見た。
(ひょっとしたらグロイス王子とあのペルツという男以外は、悪い人たちではないのかも知れない。)
そういう淡い期待がまるごと裏切られるとは夢にも思わないで、プリセアはモンボルクの町並みを眺めていた。
屋根の色も建物も祖国のカヴァルナとは違う。
(せめて、もう一度…カヴァルナを見たい。)
戦火で焼けた町はどうなっているだろうか。
親しい人たちは無事だろうか。
そう思うと胸が締めつけられる。
「どうされました?」
温かい手がむき出しになった肩に触れたので、プリセアは驚いて振り返った。
部屋にはいつの間にか、自分とジェローの二人しかいなかった。
「涙が。」
「あ…」
ハンサムな青年が紳士の手つきでハンカチを姫君の頬に当てる。
もう二人は息がかかるほど近づいていた。
「ジェロー様…」
「ジェローでけっこうです。ジェローは誠意から姫にお仕えいたします。」
「わたし…どうなるのかしら?」
彼は答えず、プリセアと同じ青みがかった瞳でじっと見つめていた。
その静かな眼差しにプリセアは「この人を信じよう」と決心した。
アルノス王を乗せた馬車がおごそかに城の前へ出てくると、民衆がいっせいに花をまき散らした。
心から祝っているというより、何でもいいからお祭り騒ぎをするチャンスにしたいだけだろう。
集まった市民には王の計らいで酒や料理が無料でふるまわれている。
もちろん高い税金で搾り取ったお裾わけというところだが。
「グロイス殿下っ、ご帰還ーっ!」
その号令にあわせて騎兵隊が槍を空にむかって突き立てる。
城壁の上からは祝砲が響きわたる。
両方の馬車が止まり、日傘をはずしたアルノス王とグロイス王子は汗まみれの顔を見合わせる。
「ただいま戻りました。」
「首尾はどうじゃ。」
「ボルゴニアの勝利にございます。」
兵士と民衆がわあっと歓声をあげても、王様も王子様も愛想笑いさえしないで太陽から逃げるようにさっさと城内へ入っていく。
ペルツが追いかける。
「花嫁様が待ちくたびれておりますぞ。」
「馬鹿な。くたびれるのはこれからだぞ。」
「さようで。うひひひぃ。」
女官を引き連れた姉のパガレアと話題のプリセア姫が門のところで迎えた。
パガレアの顔に密かな悪戯心が浮かんだのをグロイス王子は見逃さなかった。
(姉上め、何か企んでるな。女ってやつは恐ろしいもんだ。だが、こっちも負けておらんぞ。)
「おお、これはこれは麗しのプリセア姫! 今日は一段と美しい! …あとが楽しみだ…」
いやらしい声でぼそっと耳打ちする。
プリセアはぐっとこぶしを握った。
ジェローのくれたハンカチを命綱のように握りしめていた。
第5話 プリセア姫はエミリナを助け出す
長旅の垢を落とすと悪どい王子様グロイスはお昼寝に入った。
飽くことのない獣欲もさすがに疲れには勝てないのか、それとも今夜のために体力を温存するつもりか。
「待っていては駄目。これはチャンスかも…今しかないわ!」
プリセア姫には時間はあまり残されていない。
勇気を振り絞ると、アルノス王が広間で各国の王や高官から祝辞を受けているところへ乗り込んでいく。
「お、お願いがあります!」
諸外国から大勢の客が来ている今でなければ、伝統豊かなカヴァルナ王国の後継者としての発言などできない。
「…何かな? わしに用とはな。」
「カヴァルナから…参った娘たちのことです。」
一同がざわつく。
王子の女さらいは周知のことだが、表立って口にするのは結果が恐ろしい。
「あとにしてくれぬか。」
しかしプリセアは意を決して言葉を続ける。
「戦に勝てば人質をというのも分かります。ですが…女たち、それも幼い子まで…偉大なボルゴニア王国の名誉にかかわるのではありませんか?」
まわりの家来たちが青ざめて止めるようにと首を振る。
客人の中には攻められて降伏した国、その前に自分から服従した国、屈辱的な条約を結ばされて我慢している国、いつ侵略されるかビクビクしている国、いろんな事情の国の者がいたが、どこの国も大勢の女たちを人質に取られているのは同じだった。
若い姫の命がけの苦言に、アルノス王は静かに応じた。
「そのぶん働き盛りの男を残しているのだ。そのうえ食いぶちも減るではないか。」
「しかしカヴァルナでは…」
「姫よ…それ以上は申すな。」
アルノス王の態度は驚くほど同情的だ。
「カヴァルナはこのわしではなくグロイスのものじゃ。そして結婚が済めばとうぜんそなたの領地でもある。…皆のもの、下がってよいぞ! だがその前にしっかと言っておく! グロイスはカヴァルナのプリセア姫をめとる。これは決まった事じゃ!」
恐怖と好奇心で釘付けになっていた客たちは、あわてて弾かれたように広間から飛び出していった。
プリセアの無謀さに呆れて、アルノスはぼそりと言う。
「ここで騒ぎを起こしても損なだけじゃぞ。」
「私一人のことならいくらでも…でも、あの子たちは…耐えられません。」
「思いあがるな!」
急に王は髪と髭を逆立てて怒鳴った。
「お前ごとき小国の者が、ボルゴニアの気高きシェレーン家に入るなど、わしは元から反対なのだ! …奴がどうしても折れぬから…まあいい、自分でグロイスに言ってみよ。」
こうなっては行き止まりだ。
プリセアはすっかり落胆して去った。
すると柱のかげからパガレアが現れた。
「お父様、いけませんわ。可愛いお嫁さんを怖がらせては。」
「聞いていたか。ふん…ろくでなし息子にじゃじゃ馬の嫁、どうにもならぬわい。」
「うまく調教すればよろしいでしょ? 私にお任せください。」
不敵な笑みをつくって、まるで愛人にするようにパガレアは父親と唇を重ねた。
プリセアは全てを諦めたわけではなかった。
近衛兵の一人を王子の命令だと言って騙すと、女たちの監禁されてる建物へ案内させた。
だが、カヴァルナの娘たちはどこにも見当たらなかった。
事情は近衛兵も知らないという。
薄暗い広い部屋にさしかかると、折しも新しく捕虜になった女たちが帳簿につけられている。
その端にプリセアは見慣れた顔を見つけて驚いた。
「エミリナ!」
「お姉さま…いや、見ないでください! わたし、わたしぃ…」
他の女たちと同様エミリナの金髪は短く切られ、首には奴隷につけるような鉄の首枷がはめられていた。
腕や足には男の手で乱暴に掴まれたようなアザがついていた。
十四歳の従妹が受けた虐待にプリセア姫は怒りで震えた。
「この子は連れて行きます。」
「しかし…」
兵士がいぶかる。
「連れてくるよう言われたのです。グロイス様にですよ。」
「じゃあ、その…どうぞ。」
だまされた兵士たちを置き去りにすると、プリセアは泣きじゃくるエミリナを引いて自室へ連れていった。
「教えて。ね、みんなは?」
「分かりません。全員バラバラにされました。私だけ戦場に…。もうあそこには誰もいないと思います。」
ひょっとしてグロイス王子は約束を今頃になって果たしたのだろうか。
試合に勝てば女たちを解放するというあの約束だ。
でも、とても信じられない。
(もうすぐグロイス王子が起きてくる。この子を隠さないと。)
敵国で孤立無援のプリセアに誰が手をさしのべてくれるだろう。
やはり騎士のジェローしか思いつかない。
たまたま手許にあった召使いのモナの服を着せ、プリセアは従妹を連れてパガレア王女の館へ向かった。
何かあったらとジェローが教えてくれた通りに王宮の隣にある館の裏へ回り、壁にはりつくように掘られた石段を上がると、ジェローの部屋の窓のすぐ下へ届いた。
「お願い。この子をかくまって。」
「しかし、プリセア様こそ危ないことに…」
「わたしは…大丈夫。」
そう一言だけ残すと、プリセア姫は以前の強さを取り戻したように凛々しい笑顔で、自分を待つ恐ろしい運命へと戻っていった。
第6話 プリセアは道具で弄ばれ、膣にポルガを入れられる
その日の夕食の席になっても、不思議なことにグロイス王子は、エミリナがいなくなった事について何も聞かなかった。
兵士たちが恐れて報告してないのかも知れない。
でもいずれ分かることだ。
プリセア姫はいっそ自分から打ち明けてしまいたい気にもなったが、それも変だ。
あれほど口論したアルノス王も、まるでちっとも機嫌など損ねていないように平然としている。
皆の静かさがプリセアには不気味だった。
夕食が終わると、グロイス王子はプリセアをこれまでとは違った部屋へ導いた。
扉の前ではあの変態中年ボン・ペルツがそわそわしながら待っていた。
「ようやく姫様のお部屋が整いましてなあ。いやー、金がかかりましたぞ。」
「前置きはいいから、ペルツ、早く見せてやれ。」
「きゃっ!」
どうせ粗末で陰気な部屋だろう。
そんなプリセアの予想は完全に裏切られた。
これまでの物置のようなのとは天と地ほども差がある豪華で優雅な内装だった。
白さのまぶしい漆喰の壁には草模様が描かれ、タペストリーをかける金具には鹿の角が付けられていた。
高くて広い窓には滑らかな板ガラスがはまっている。
しゃれた椅子に張ってある布は色とりどりの刺繍で飾られ、天蓋つきの広いベッドには真珠のような輝きの上等なシーツがかけられていた。
そして天井からは金の鎖でシャンデリアが下げられ、室内を昼のように明るくしていた。
プリセアにはグロイスという男が分からなくなった。
自分を奴隷が家畜のように蔑んだかと思えば、急にこんな贈り物をするとはどういう神経なのだろう。
「気に入ったようだな。」
満足そうなグロイスの声がプリセアの胸をちくりと刺した。
この粗暴な王子様がやっと見せた人間らしいところが、エミリナの失踪を知ればどういう変化をするか、想像もしたくない。
しょせん生け贄だと諦めて身を任せるしかないのだ。
「さあ姫、よく見るがいい。」
背中を押されてプリセアは中へ入る。
ガチャリと鍵がかけられ、彼女はうろたえた。
「どうして、その人までいるんですか!」
「ペルツ。おい、お前が邪魔だとさ。」
「こりゃヒドイ! せっかくグロイス様のお留守の間、誠心誠意でお世話しましたのに。」
「で…出ていって! お願い、この人を出ていかせてっ!」
この変態の目に裸をさらすのはもう耐えられない。
恥毛を剃られてしまった体をグロイス王子に見られるだけでも死にたいほどなのに、二人がかりで侮辱されるなんて気が狂いそうだ。
「おいペルツ、お前の教育はどうなってるんだ? 姫のワガママがちっとも直ってないじゃないか。」
「なになに、これを見せれば…」
ペルツは大股で奥の壁のほうへ行き、ロープを引いてタペストリーをまくり上げた。
壁いっぱいを覆っているように見えたタペストリーの向こうには、実はこの部屋の残り半分が隠されていたのだ。
「おおっ!」
「あああぁ…」
こっち半分とは対照的に、黒っぽい石の地肌がむき出しになって、床や壁や天井からは鉄の鎖がいくつも生えていた。
そして重罪人の拷問に使うような、何本ものベルトがついている鉄製の椅子やX型の木の台が並んでいた。
横の棚にはボン・ペルツが買いそろえたと思われる卑猥な道具がずらっと陳列してあった。
「女盛りの若妻にとって素敵な部屋じゃないか! なあプリセア。」
彼女はがっくりと膝をついて、その凶悪な風景を呆然と見ていた。
「いや、いやいやぁ! ゆるしてえええっ!」
鉄の拷問椅子をガタガタ揺らして、カヴァルナの美しき姫君はすらりとした脚の間から淫らな汁を飛ばした。
ペルツとは違っていっさい遠慮のないグロイス王子の責めは、拘束されて逃げ場のない肉体には辛すぎる。
「いっちゃう! また…ひゃっ、あう! いっちゃうぅ、うあああああ!」
「だらだら垂らしおって、堪え性のないカラダだな。」
新品だった水色の長靴下も滴る体液にぐっしょり濡れてしまい、肌の色を透かしている。
グロイスは長くいびつなソーセージ型の淫具で、守る毛を剃られてしまった裸の割れ目を擦りまくる。
「…もう無理です…やっ、無理ですうぅ! 待ってえっ、また…きゃああああああっ!」
「グロイス様、もうそのへんで…。道具が壊れます。」
「ふん、こっちの手も壊れそうだ。お前も何か余興を用意してるんだろう?」
「それはまあ…えへへへへ。」
プリセアがぐったりしている隙に、ペルツは部屋に新客を招く。
小麦色の肌にウェーブの髪。
召使いのモナだ。
乳首が透けるほど薄手の肌着一枚だけで下には何もない。
プリセアと同じで毛さえない。
「おう、お前が例の…。お前の主人は、ちょっとお休みのようだが。」
「はい、代わってご奉仕いたします。」
膝をついて男のズボンの合わせを探ると、布の間から屹立した肉が飛び出す。
「大きい…です。」
熱を顔じゅうで感じようとするみたいに愛しそうに頬ずりしてから、丹念に舌を這わせる。
「ふあぁ、…あう…ふううん、ふああぅ…」
ゴツゴツした幹が唇に触れる感覚だけで、モナは息を荒げてうっとりと頬を紅潮させていた。
そして滑らかに膨らんだ先端を含んでは、赤ん坊のようにさかんに吸いたてるのだった。
「ご主人さまぁ…あの…」
「なんだ? ご褒美が欲しいのか? いかん、仕事が終わってからだ。」
「でも、もう私…」
「しょうのない娘だ。どいつもこいつもしつけが成ってないな。ペルツ、あれを出してやれ。」
ペルツがポケットから黒い丸薬を取り出すと、モナはあわてて手を伸ばした。
だが、グロイスはそれを受け取って拘束椅子のプリセアをじろりと見た。
そして…
「うあ…な、なに? あっ、イヤ、何をするんです!」
夢うつつだったプリセアはたちまち現実に引き戻された。
男の手が強引に股間を押し広げている。
「嫌っ、変なもの入れないで! ああっ、きゃあぅ!」
グロイスは丸薬を二本の指にはさむと花嫁の胎内にずぶずぶ押しこんだ。
不意打ちのことでプリセアはつっぱるような痛みに顔をしかめた。
そしてグロイスは姫君のお腹を指さすと、こう言ってのけた。
「モナ、お前の欲しいものはここだ。勝手に取るがいい。」
「え? モナ? 何で…」
いつの間にかモナが現れたことにプリセアは動揺した。
そしてペルツがモナを後ろ手に縛っているのを見て、ぞっとした。
次に何が起こるのかグロイスは興味津々というようすだ。
モナはウェーブの髪を振りみだして哀願する。
「意地悪はおやめください。私、もうっ、もう駄目ですぅ。」
「あ…あなた達、モナに何をしたの?」
「ポルガという薬を知ってるかな?」
その言葉にプリセアはぎょっとした。
それでモナがペルツのような男の言いなりになっている理由が飲みこめた。
痛み止めのポルガは使い方しだいでは精神を壊して操り人形のようにしてしまうという。
モナは一時も我慢できないようすだ。
「グロイスさまぁ、お許しください! お…お薬をっ!」
「モナ、頭を使え。いや頭じゃなくて…ほら。」
そのヒントで少女はやっと方法に気づいた。
もちろんプリセアも。
「やめて! いけないっ、モナ! 人が見てるのよ!」
モナは口を大きく開けて舌を突きだしながらプリセア姫の股間へと迫る。
プリセアはお尻をふって逃れようとするが、鋼鉄の椅子がそれを許さない。
世にもいやらしい拷問が始まろうとしていた。
「や、お願いっ! モナぁ…駄目よっ、やめなさいっ! やめてええええーっ!」
第7話 プリセア姫はモナの舌に姦される
召使いのモナは魂を失った人形のような顔で、おびえている若い女主人に迫った。
「やめなさい! ね、しっかりして、モナっ!」
プリセアがどれだけ懇願しても聞こうとしない。
乾いた唇から唾液にひかる舌をぺろりと出して、黒髪のかかる顔を姫君の高貴な秘部によせていく。
足を閉じたくても全身を鉄製の椅子に革ベルトで固定されてしまってはムダな抵抗だ。
「そんな…うあ…」
ぬるんと入ってくる感触。
プリセアは身震いした。
男の手で強引に何度もイカされたあとでは柔らかい舌の愛撫は心地よくさえ思えた。
「モナぁ…はあ、そこは…そこ、やあんっ! ああっ…はあああ…」
主人の体内を舐めつづける召使い。
でもモナにとって今の主人はプリセア姫ではない。
火照った肉の穴のもっと奥にある薬、ポルガという魔薬の塊がモナを支配しているのだ。
(出てきて。はやくぅ! 欲しい、欲しいっ!)
プリセアがしとどに溢れさせる蜜の中にかすかな薬の味を感じて、モナの舌は別の生き物のように粘膜の壁をえぐりまくる。
「ひゃあぅ! だ、駄目よお…モナ、そんなの。ううぁ…はあああっ!」
(いけない。感じちゃ。こんな男たちの前で…女同士でなんて。)
何度経験しても快楽に乱れているのを人に見られるのは嫌だった。
生まれながら高貴な王女として自分を律してきたプリセア姫には、一番卑しい姿を人目に晒される屈辱は死ぬほど辛かった。
でも、カヴァルナが落ちてからのたった一月半の間に、彼女のカラダは淫売の業に染まってしまったみたいだった。
「はんっ! ああん、あん、あんっ! ひああっ!」
いつしかプリセアの喘ぎは赤ん坊みたいな甘えた声になってきた。
モナの舌のせいもあるが、彼女にも少し薬がまわってきたのだ。
体内に押しこまれた固い丸薬も、たくさんの愛液と蠢く媚肉のヒダのせいでだんだん溶けてくる。
モナはその汁を一滴も逃さないようにと口全体を使ってプリセアの股間に吸い付いていた。
「んむうっ! んんん、あむうううっ、んーっ!」
(姫さま、ごめんなさい! ごめんなさい! だって…おクスリがっ!)
中毒にされているモナの精神は禁断症状には逆らえなかった。
モナは後ろで縛られた手を自分自身のお尻に届かせると、そんな自分を罰するように指を何本も秘所に挿しこんで掻きまわした。
モナの股間からもプリセアに負けないほどの粘液が滴っている。
グロイス王子は向こうで冷たいシャンパンをやりながら呆れ顔だ。
「おい、ペルツ。女同士でこの始末じゃあ、こっちの出番なしだな。」
「なにをおっしゃいます。この後のアレが楽しみなんでごさいましょ? ひひひひ。」
「まあな。だが、アレをやっちまって姫の頭が狂わなきゃいいがな。」
男たちの話も煩悶している娘たちには聞こえなかった。
モナの上唇がクリトリスを擦るたびにプリセアは小さな絶頂を繰り返した。
その波はどんどん大きくなって彼女の意識を飲みこんでいく。
「ひゃああああん! ひいっ、くああっ! きゃうん! きゃああああんっ、あんっ!」
革ベルトで擦れて血がにじんでもプリセアには痛みなど感じられない。
全身の肌という肌を官能の稲妻が駆けめぐっている。
びくびく跳びあがるお尻の下で自分の流した体液がぐちゃぐちゃと淫靡な音をたてているのも、背を反らすたびに鋼鉄の拷問椅子がキイッときしむのも、生け贄の姫君の堕落のさまをあざ笑っているかのようだ。
恥ずかしいのに…そうじゃない、恥ずかしいほど気持ちよくなってくる。
(あの薬…ポルガが、私にも…)
でも薬が効いてきているとしても、プリセアは自分の心が肉欲に負けてしまうのが許せなかった。
女だというだけで運命を決められてしまう、そんなのは自分らしくない。
そんな自分は許せない。
そして自分を駄目にしてしまうモナも。
モナはただ薬ポルガのとりこ。
相手の苦しみなんてお構いなしに、歯まで立ててプリセアの女を刺激する。
「ふうーっ! ううん、あううっ…んむううーっ!」
一時も緩まない責めが続き、召使いの裏切りに姫君はついに屈した。
氾濫した川が堤防を壊すように限界を超えた痙攣がプリセアの五感をバラバラに砕いた。
「許さないっ、ゆる…さないからあっ! いあああっ、モナああああああああーっ!」
搾りだすように絶叫してプリセアが果てると、胎内の圧力に押し出されて半分ぐらい崩れた塊がモナの口へ飛びこんできた。
モナは主人の噴き出すしょっぱい体液といっしょに薬を飲みこみ、やっと安心したように気を失って倒れた。
拷問椅子から下ろされてベッドに運ばれても、カヴァルナの姫君は気力の抜けきった様子でうわごとのように呟いていた。
「いく…あ、また…わたし…ダメ、こんなぁ…」
グロイス王子は花嫁の乱れた栗色の髪をわし掴みすると、汗と涙と唾液でべとべとになった顔を見つめた。
「…ゆるして、もう…い、いきたくない…」
「だいぶ女らしくなったじゃないか。」
だらしなく開いた口に舌を入れて濃密なキスをする。
男のぶ厚い舌で口を侵されて、プリセアは何もかもがどうでもよくなってきた。
誰の花嫁だろうと性奴隷にされようと、全てを薬のせいにして快感に身をまかせてしまいたい。
どうせ逆らえない運命なら流されてしまえばいい。
そうするしか…
プリセアの両腕はいつしか男の背を抱いていた。
第8話 プリセア姫はグロイス王子に姦される
まるで赤紫色をした蛇のように、縛られたあとのアザが二十二歳の女体に絡みついている。
ま新しい純白のシーツの上では全身の肌もほんのり赤らんでいるのが分かる。
長い栗色の髪はしっとりと汗をふくんで、女にしては肉付きのいい肩から乳房にかけて張りついている。
荒野に咲く小さなバラと言われたカヴァルナ王国の自慢、戦う美しき姫君プリセア。
それも今は見るかげもなく、悪どい王子様の愛撫にくんくん鼻を鳴らして喘いでいた。
「おてんばも可愛くなってきたな。濃い蜜が滴っておるわい。」
「あぁ…うぁ、はあ…はんっ、くああん…」
彼女はもう自分から膝を開いて男の指を受け入れている。
目を閉じたまま赤ん坊のように指をくわえたり、ときどき切なそうに乳房を搾ったりして、年頃になった肉体が作り出す快楽に溺れている。
妖しいポルガという薬の成分が秘部の粘膜から進入して、彼女の気丈さを奪ってしまったのだろうか。
おへそがヒクヒクしてきたのをグロイス王子は見逃さない。
「そろそろ入れて欲しいか? ずいぶんご無沙汰で花婿のコレを忘れてはおるまいな。」
太股の内側に熱いカタマリが触れるのをプリセアは感じてうすく目を開ける。
軍事大国ボルゴニアの王位継承者の自慢する逸品が、彼女の秘めやかな神殿に突入しようと脈を打っている。
「い…」
嫌と言うつもりなのに、薬のせいか口は勝手に違う言葉をつむぐ。
「入れて…」
姫の敗北宣言にグロイス王子のものは一段と大きく膨らんだ。
獲物に襲いかかる猛獣のように逞しい男の体がプリセアの上に覆いかぶさる。
半分崩れた城壁のように口を開いていた媚肉の門は、たちまち巨大な肉の丸太で貫かれた。
「くうぁ、あああああああっ!」
男を飲みこみながらプリセアの背は弓のようにしなって浮きあがった。
両手が空中をさまよったあと相手の背にしがみつく。
「…ああぅ、んっ! はああうっ…」
「嬉しいか! そうら、奥まで届いてるだろ!」
「は…はい。」
そう答えるプリセアの泣き顔はきっと嬉し涙だ。
女の奥に潜んでいるケモノの本性が、プライドや義務感といった心の檻から解き放たれて、今この瞬間の官能を純粋に味わっているのだ。
「きゃっ…あっ、ひゃあんっ! あああん! うああーっ!」
「それっ、どうだ? こうしてやるぞ。」
もったいぶらずに抜き差しの運動をし始める男。
作り物でないホンモノの男の肉にプリセアの肉も歓迎するかのようだ。
一ヶ月半も前、処女を奪った時からは想像できないほど、彼女の体は柔軟に相手を包みこむ。
「あうっくぅ…くあああんっ! いっ、ひああ…あぁ…」
毛を剃られてむき出しになっている肉芽を、ゴツゴツとした幹に荒っぽく擦られて、プリセアは壊れたオモチャのように全身をわななかせた。
先に召使いのモナの舌でさんざんに弄られまくったせいで乱暴な責めも心地いいぐらいだ。
「くああ、うあああっ! んうっ! ひいいっ、い…あうううっ!」
(駄目、こんなの…か、感じ過ぎる! 恐いよおっ!)
男根がずしんと押し入るのに合わせて下腹から脳天にむかって稲妻が走り、手足の先までが痺れる。
バラバラになってしまいそうな感覚に耐えようとするのか、プリセアの四肢は憎いはずのグロイスに絡みついていた。
部屋の向こうのほうでは変態商人のボン・ペルツが、いやらしい目を細めて二人の愛欲の踊りを見守っていた。
あまりじっくりと見守り過ぎたため股間の分身が勃ってしまった。
「おい、嬢ちゃん…起きろっ!」
呼びかけて揺すってもモナは床にぐったりとなって目を覚まさない。
薬と疲労のせいで眠りの中だ。
薄い肌着ごしに乳首が立っている。
淫らな夢を見てるに違いない。
「まったく自分勝手なことよ。このカチカチのものをどうしたもんかのう? もう一人ぐらい肉奴隷を作っておくべきだったわい。 よいしょっ!」
文句を言いながらペルツは顔をまっ赤にしてモナを椅子へ持ちあげた。
そして力の抜けきった女の片足を肩にかつぐと、肌着に透ける小麦色の乳房に顔をうずめながら、下着も恥毛もない裸の淫花に尖った肉棒をつき刺した。
「ふあああ…ひっ、ひあぅ…」
夢見ながらモナが喘ぐと黒髪が波うってペルツの禿頭を隠した。
「ひいぁ…また、駄目っ、またイクのおおっ! あっ、きあああああんっ!」
「おっ! ぐうっ…」
甲高く鳴いて絶頂したプリセアの締めつけに、グロイスは射精を惜しむように堪えた。
尿道を走る精の高まりをいったん腰を引いてやり過ごすと、再び火照った肉の奥まで収めておいて休憩に入った。
グロイス王子は改めて串刺しにされた姫君を見おろす。
その高貴な秘所は身分に似合わず淫らにひくつきながら男根のあちこちを刺激してくる。
「また一段と男を狂わせるカラダになったな。おいペルツ、誉めてやるぞ。」
「うひひっ、そう言われますと私めも光栄です。」
無意識のモナを姦しながら調教係はそうお礼を言った。
「さて…と、そろそろ楽しむかな。」
グロイスは枕を引き寄せるとプリセアのお尻の下へ押しこみ、彼女のすらりとした両足を上へ持ちあげた。
自然とプリセアの胴は逆立ちぎみにくの字に折れて、男根を突き当たりまでくわえこんだ。
男の手がみょうに優しく頬を撫でてくる。
この男がこういう優しさをみせる時は決まって悪い魂胆があるのだ。
グロイスは囁くようにプリセアに聞く。
「あのポルガって薬に子袋を緩める作用があるのは知ってるか? どういうことか知りたいか?」
ぐいと腰を落とすと、男の鉾先が行きどまりの壁の上へ当たる。
「ここだ。」
「くうっ!」

内臓を押される感覚にプリセアは苦しげに眉をひそめた。
もし目で見ることができれば、そこには子宮の口が丸い丘のような形をして静かに男の精を待っているのが分かるだろう。
そんな聖なる門に向かってグロイスが何を企んでいるのか、プリセアには予想もつかなかった。
第9話 プリセア姫は子宮の中まで姦される
「あの薬のせいで、ここが緩むとな…面白いことができる。」
グロイス王子はそう言いながら、残酷な計画をいきなり行動にうつす。
欲望に凝り固まった男の肉の杭でプリセア姫の体を深々と貫くと、その行き止まりのさらに奥めがけて押しこもうとする。
無理矢理な突進にプリセアは悲鳴した。
「いやっ、くっ、苦しい…無理ですっ、ダメえええぇっ!」
しかし悪魔の薬ポルガの効果はてきめんだ。
彼女の子宮の口はゆるゆると広がって、通すはずのないものを受け入れようとする。
「おお、すごいぞ。プリセアぁ…分かるか? 入っていくぞ!」
「痛ああぁ…うあ、あぐ…」
わけのわからない苦しみに翻弄され、彼女は呼吸さえもできない。
「うおお、入っていく、入っていくぞおっ!」
グロイスには女の奥底に隠れた器官が、男性の先端をゆっくりと飲みこんでいくのが感じられるのだ。
本来なら入ることのできない場所を侵略していく、牡として最高の快楽だ。
「あ…ひっ…い、ひいい…うあああ…」
容赦ない攻撃に女の閉ざされた聖域はきしみながら侵されていく。
プリセアは自分の膝の間で顔じゅう脂汗を流しながら歯を食いしばった。
体を折り畳まれて押さえつけられた姿勢ではわずかに逃げることもできない。
槍に刺し殺される死刑囚のような絶望のいっぽうで、痛みを超えた不気味な狂悦が迫ってくるのが恐ろしかった。
そしてついに肉の輪をくぐって男根の頭が子宮の内にぬぬっと滑りこんだ。
「ひいいいっ! くああっ…ふわあああああああーんっ!」
その瞬間、プリセアは苦しみとも喜びともつかない甘い叫び声をあげて悶絶した。
(私、何をしてるの?)
プリセア姫はぼんやりと自問する。
濃い霧のむこうに自分の姿が浮かんで見える。
二本の足をバンザイするように肩のほうへ倒れさせて、毛を綺麗に剃られた恥ずかしいところに浅黒い男の肌を密着させている。
人間というより淫らな別の生き物みたいだ。
(プリセア、ねえ…あなた、どうしたいの?)
どうなってもいい、と言いたげな恍惚とした顔で自分が見返してくる。
夢半分で心が漂っている、そんな快楽の波間だ。
「うああああーっ!」
叫びながら意識を取り戻したのは突然、体の芯を抉られたせいだ。
大きな出っ張りが押し入ってきて心臓まで突かれるようだ。
「プリセア、気を失っててはもったいないぞ。こいつはめったに経験できないぞ。」
グロイス王子のまっ黒な瞳が彼女を睨んで笑っている。
猛獣のような冷たい目に欲望だけが燃えている。
「な…何、これ、何なの…」
うろたえるのも当然だ。
プリセアのお腹の奥では男の陽肉がふつうではない形に填りこんでいるのだ。
「言っただろ。薬のせいで子袋が緩まれば、女の穴の底が抜けてしまうわけだ。」
「そんな…」
体を壊される。
プリセアはそう思って恐ろしくなる。
でもいくら逃げたいと願っても全く身動きができない。
男女の肉はしっかりと繋がりあっていて、相手がほんの少し体を揺らすだけでも耐えがたい。
だというのにグロイス王子は花嫁に対する心配りなど微塵もないのだ。
「あっ、やっ! 動かないで…ひい、あああぁ!」
太い肉の槍がずるずると抜かれていく。
男根の幹は見た目にはまっすぐでも表面には微妙な凹凸がある。
それを身をもって感じる。
「はああああ…うあっ…あ…あぁ…」
バカのように口を開けてプリセアは内臓を引き出されるような不気味な肉感にもがく。
「プリセア、そんなにコレが気に入ったか? ずいぶん締めつけてくれるじゃないか。」
グロイスはそれを味わうように腰を使ってぐねぐねとこね回す。
するとプリセアは白目をむいて、いっそうだらしない声で喘ぐ。
「くあ…あああぅ。ひっああ…あうぁ…あ、いっ…はああっ!」
高貴な生まれを忘れて痴態をさらすプリセアのさまを、男は時間をかけてじっくり楽しむ気なのか、驚くほど遅くじりじりと抜き差しをする。
それが堪らなく辛い。
(もっと動いて…駄目、そんなの駄目! でも…)
プリセアの青みがかった瞳が、物乞いする眼差しで男を見つめては、急に恥じるようにそっぽを向く。
彼女の中で快楽に身を任せてしまいたい葛藤が起こっているのを、グロイスは見逃さなかった。
「さあ、このグロイスの女になるか?」
「…あああんあぁ…あうああぁ…」
「どうだっ?」
腰をぐっと突くとプリセアは切ない声で鳴く。
「ひああああっ! な、なりますっ!」
自分が言ってしまった言葉にプリセア自身驚く。
でも彼女にはもう他に道はないのだ。
「…私、なります…グロイス様のものに…」
「口先だけではなく、お前の心と肉体の全てがだ。いいか?」
「ああ、んあああぁ! はい…な、なりますっ!」
アザだらけの手首が愛しそうにグロイスの背に回される。
人の心なんていざとなれば脆いものだ。
プリセアの気高い魂はわずか二ヶ月たらずの間に肉体の奴隷になってしまった。
それでも、苦痛で責められたのだったら彼女は最後までプライドを失わなかったかも知れない。
しかしカヴァルナの戦う姫は、快楽の責めには無防備すぎた。
「私ぃ…ぜんぶ…グロイス様に…あうっ、さ…捧げます。」
「よく言ったな。よおし、じゃあ動くぞ。」
「してっ、してくださいっ!」
(誰か、私を…こんな私を殺して!)
そう心の中で叫んだ時、カヴァルナのプリセア姫は自分を失った。
あとは肉欲に支配された淫婦がよがり狂っているだけだった。
第10話 プリセア姫は子宮に射精され失神する
はあっ! はあっ! はあっ! はあっ!
荒い息づかいが部屋にこだまする。
王子様とお姫様が仲良く遊んでいる…と言うには、あまりにも卑猥な光景だ。
ベッドのシーツをしわくちゃにしながら汗と体液にまみれて男女が絡まりあっているのだ。
「またイキそうだな。おい、これで何度目だ?」
「い、言わないでえっ…ああぅ、ひっ、ひあああっ!」
「ほらプリセア。イク時はちゃんと言え!」
グロイス王子が女の股を左右にぐいと開いて突きこむと、プリセアは両足をほとんど一直線につっぱらせてエクスタシーに悶える。
子宮の口まで男をくわえこんでいる凄まじい快感は、彼女に羞恥心を忘れさせるには十分だった。
「うああんっ! あ、ああくぅ…イク、イッ…イクうううーっ!」
「いいぞ! もっと締めろ!」
馬を手綱で御するように悪どい王子は腰をぐりぐりと動かすと、がっちりと填りこんだ男根でもってプリセアを快楽の道へ走らせる。
「ああ…わああっ! あひぃ、ひいいあああっ!」
「イケえええ! もっとイクんだっ!」
「あひいい、いやああああーっ! くあああっ! 死んじゃうううぅ!」
幾度となくオーガズムの坩堝に突き落とされ続けて、プリセアは精神が擦り切れてしまいそうだった。
(狂うわ。このままじゃ、私、狂ってしまう!)
「ゆ、ゆるし…いああああ! ひいっ! ひいい…んああああっ!」
巨大な武器で底なしに貫かれるだけではない。
腰がドシンとぶつかって来るたびに、プリセアの花園の上に光る敏感な真珠が、男の肌に荒っぽく摩擦される。
その上に乳房を揉まれ、ときどき深いキスを受ける。
「ああむ、んぐう! おうう…うぐ、んむうううあっ!」
口を塞がれると息もろくにできない。
その苦しさが快感を爆発寸前にまで高める。
意識が混乱するうちに全身が肉欲のカタマリになってしまう。
「ぷはあっ! うあ、くああっ! いや、いや、またっ…ひいいいいっ! イ、イクッ!」
下半身が壊れたように緩んで、熱いものが迸る。
「おっ、プリセア! いい年してお漏らしかぁ?」
「あ…いやああっ、見ないでえっ! ひああああん!」
恥ずかしいという気持ちよりも放尿の心地よさのほうが勝ってしまう。
プリセア姫のお下はぴゅっぴゅっと断続的におしっこを噴いては、グロイス王子との繋がりをなおさら潤していく。
そして愛液と混じって下品な臭いをさせる。
プリセアの醜態に刺激されたのか、グロイス動きが激しくなってきた。
限界が近いのだ。
「おお、いくぞっ! お前の腹の奥に…子種をぶちまけてやる!」
「そんなぁ、駄目ええぇ! 嫌ぁ!」
頭を振って懇願すればするほど、グロイスの肉根はますます固くいきり立ってくる。
「ゆっ、許してぇっ! グロイス様…駄目ですっ、許してえええええっ!」
涙と汗でぐしゃぐしゃになっているプリセアの顔を掴み、自分の顔を擦りつけるほどに寄せると、グロイス王子はほとんど殺気までこもった恐ろしい責めで美しい姫君を蹂躙した。
「うおおおおっ、出すぞぉ! 孕めええええっ!」
「きゃあああっ! 嫌あーっ! イクううっ! いやぁ、うわあああああああーっ!」
ブシュウッと大量の精液が子宮のまん中で噴き出される。
プリセアはかすれた悲鳴をあげながら男の大きな体の下で全身をつっぱらせて強烈なオーガズムの稲妻に激しく痙攣した。
いくら達しても終わらない長い絶頂。
頭の中が沸騰しそうな官能の爆発だった。
「…ああぁ…あ…ああああああぁ…」
泡を吹いて呻きながらプリセア姫は失神している。
彼女の腹の中ではまだグロイスのものが射精の残りを楽しんでいる。
男の分身は子宮の口に挟まれたまま萎んだり膨らんだりを繰り返しながら、白い粘液の最後の一滴までも吐き出してしまおうとするようだ。
「プリセア、お前は私のものだ…永遠に私の奴隷だ。」
「…あは…あはははっ…」
聞こえているのかいないのか、プリセアは痴呆めいた笑みを浮かべて、いつまでも快感の作る小さな痙攣を続けていた。
第11話 プリセア姫は兵士に剣の稽古をつける。
ボルゴニア王国の首都モンボルクでは町をあげて、グロイス王子の戦勝を祝う盛大なパーティが続けられている。
大軍は長い長い列をつくって帰り、その最後尾が到着するまで三日もかかった。
アルノス王の布告では、しばらくは国力を回復させるために戦争をしなという。
それで兵士たちの家族も畑をほうって都まで迎えに来ていて、町中が喜びの声で騒がしくなっていた。
しかし侵略されたほうの国々にとっては暗黒時代の始まりのようだ。
お祝いの献上品を持ってくる各国の王侯や使者たちは、青ざめた顔につくり笑いをして宮殿へ進んでいく。
そして、人質にとられる姫君たちは着飾ったドレスとは反対に死人のような固い顔をして、王宮の門をくぐっていく。
門の上ではボルゴニアの紋章の獅子が不幸な人々を見下している。
その同じ紋章が、エミリナの白い肌のうえに焼きつけられていた。
カヴァルナの王族の一人として、世間の荒事とは無縁な暮らしをしてきた彼女だった。
たとえば「バラが欲しい」と言えば家来が棘を削って渡すほどの、何も苦労も知らない十四歳だった。
それがこの春にボルゴニア軍がカヴァルナに攻めてきてからは、一生分をこえるほどの苦難を味わわされた。
人質として牢に入れられ、ひどく粗末な食べ物と不衛生な水、その上に戦場に連れていかれて....
(嫌! もう、思い出したくない!)
戦場で受けた虐待は毎夜のように悪夢になってエミリナを襲う。
汗臭いケモノのような男たちがエミリナの上に覆いかぶさってくる。地獄の記憶だ。
「う....ああ....」
「大丈夫ですか?」
うなされてる彼女に声をかけてきたのは騎士のジェローだ。
プリセア姫に頼まれてエミリナを匿っている。
この城でただ一人の信頼できる男。
エミリナはむくりと起きると小さくうなづく。
でもジェローの手が伸びてくるとビクッと反射的に怯えてしまう。
ジェローは少女の髪をそっと撫でつけて、励ますように微笑みかける。
(....こういう方なら。)
エミリナ姫の中に恋が芽生えるのも不思議ではない。
けれど今の彼女はその気持ちを自覚できるほど平穏ではなかった。
ボロボロになった体と心を癒すためには時間がいる。まだ長い時間が。
「お従姉さまは?」
「プリセア様からはまだ知らせがありません。ひょっとしたら挙式が済むまでここへは来れないかも。」
「結婚ですか。」
「グロイス王子とです。」
グロイスの名前が出たとたんエミリナの全身に悪寒が走った。
少女の人生をめちゃくちゃにした一言「好きにしろ」、その声が耳の奥に響く。
そして襲いかかってくる兵士達の姿が....
「いやぁ!」
頭をかかえてうずくまるエミリナをジェローは思わず抱きしめた。
彼女が何をされたのか、教えられなくても彼には予想できた。
全身のアザと擦り傷、そしてお尻につけられた焼き印のせいで。
その頃、プリセア姫は質素なキルト服に鎖編みの籠手をつけて大広間にいた。
木の剣を勢いよく振り回して若い兵士たちに稽古をつけている。
力任せに打ちかかってくる男の剣を軽く流して脇腹へ切りつける。
技が決まるたびにアルノス王が銀のカップを打ち鳴らして誉める。
プリセアの技は伝説の名剣士アルター・フォーンの教えを受けたもので、誰にも真似ができない見事なものだ。
相手が剣でも槍でも斧でも、それぞれに工夫して対応できる。
五人しか弟子を持たなかったというフォーンの弟子の一人が彼女なのだ。
プリセアにとっても、こうしてひたすら体を動かしているほうが苦しみを忘れられる。
変なイタズラをされなければ、剣を使うことはプリセアにとって一番の気晴らしだ。
「次っ、次は?」
「では拙者がお相手します。」
前の人が落とした木剣を拾って男は打ちかかってくる。
とても素早い。
受け身と攻撃がなめらかに繋がっていて、プリセアの剣にも似ている。
しかしカヴァルナの姫君のほうが一枚上だ。
男の背中に自分の背をあわせるように密着して、相手が迷ったところで剣を絡め取ってしまう。
「ひえっ!参りました。降参....」
「十分じゃ。」
アルノス王の命令と皆の笑い声で稽古は終了。
先日の口論で気を悪くしていた王も、このサービスで姫を許したようだ。
冷たい飲み物をすすめる。
「夫婦ともども武勇を誇ればボルゴニアの将来は安泰だ。」
「父上、武勇だけではございませんぞ。」
後ろから声をかけたのはグロイス王子だ。
プリセアの首筋を撫でてキスして見せる。
アルノス王はにやりとしてさっさと去る。
そう当てつけるなと言わんばかり。
「さあ姫、汗を拭いてやろう。」
耳元でそう囁かれてプリセアはぞくりとする。
嫌悪感ではなく期待が湧きおこって、とっくに熱い体をもっと熱くしてしまうのだった。
第12話 プリセア姫はグロイス王子の言いなり。
剣の稽古が終わったプリセア姫は、グロイス王子に連れられて控えの間へ入った。
小さなテーブルと椅子があるだけの小部屋だ。
王子は二つある扉に閂を下ろすと、勇ましい花嫁を脱がせにかかる。
厚い布を何枚も縫い重ねたキルト服は汗を吸ってじっとりと湿っている。
後ろに束ねた髪も解けば湯気が出そうなほどだ。
いつもなら侍女たちが着替えさせてくれるが、こうして男の手で剥かれていくのはとても恥ずかしい。
「すごい汗だな。」
キルト服の下には肌着一枚きり。
汗でべったり張りついて乳首が透けている。
グロイスの指がその先端を弾くとプリセアはくんと鼻を鳴らす。
乳首から胸全体に刺激がじわっと広がっていく感じだ。
下半身は左右に割れたズボンで股間だけ別に布が当ててある。
腰ヒモから股布をはずすと股間だけが裸になる。
「あ....あ....」
「期待してるのか? 可愛いやつめ。」
プリセアの背を押して窓辺のテーブルにむかって手をつかせると、グロイスはお尻の間に顔を埋めた。
「匂うぞ。汗だけじゃないな。」
「やああん! ああ、い....ひゃあんっ! あっ!」
お尻をぷるぷる震わせてプリセアは甘えた喘ぎをする。
栗色の髪を乱して窓から見える空に向かって恥ずかしい鳴き声をあげる。
青みかがった瞳はうつろだ。
「きゃああぅ! だめぇ、そこ....ああっ、うあああん!」
汗が雨のように石の床に落ちて、小さな部屋じゅうが酸っぱい女の香で満たされる。
「そんなに喚くと広間の連中に聞こえるぞ。」
「ああ、でも....いやあっ! もう!」
肌着ごしに自分の乳房を搾ると汗が指の間から滴る。
濡れた手で頬をおおい、しょっぱい指を口に入れる。
テーブルの板を引っ掻いて悶えてはお尻を突きだす。
もっと舐めてと言わんばかりだ。
(私、どうしてこんなに変わってしまったの? あんなに憎かったのに....いいえ、今でも憎い! でも体が....)
「お、おかしくなるっ! こんなの....うあっ、ひあああっ!」
テーブルをガタガタ言わせてプリセア姫は小さな絶頂を伝える。
グロイス王子は髭についた愛液を拭って、彼女に肌着を脱ぐように命じながら、自分のほうでも大きく張った男の竿を出してみせる。
「ほら、しゃぶれ。」
プリセアは嫌がりもしないでグロイスの前にひざまづくと股間に顔を寄せる。
調教されきった女の姿だ。
男のモノもかなり汗臭い。
でも匂いのキツさが彼女の心をかえって刺激する。
惨めな自分に興奮してしまうのだ。
「どうだ、俺様のはうまいか?」
「....はい。」
顔を掴まれ肉棒で舌をごしごしと擦られるとプリセアは涙目になって鼻をくんくん言わせる。
「うぐっ、んくぅ....あむうう....くうんっ! んぐうぅ....」
やがて手が自然と股にのびて濡れた花びらをさぐる自慰を始める。
底が抜けた蜂蜜の壺のようにプリセアの淫らな穴からは温かい粘液が止めどなく漏れていた。
「うーっ! あむぅ、んんくあぁ....んあ、むううーっ、あうっ!」
「もっとマジメにやらんか!」
喉を突かれる苦しさと下半身の刺激とでプリセアはもう何も聞こえないほどだ。
左手で媚肉を広げ右手で赤い真珠とヒダを擦りあげる。
また指を奥へ挿しこんでは深く深く掻きまわす。
「うあ....あぐううう! くうあっ、んんうっ! ぐぅ....うああっ、んむあああああーっ!」
また勝手にオーガズムを貪る。
やっと男根から放されてぜいぜいと荒い息をする彼女をグロイス王子はにやにやと見下ろしていた。
また何か企んでいるらしい。
プリセアは顔をあげる。
汗と涙と涎で汚れた顔。
「....下さい。」
「ここで欲しいのか? 声を聞かれたらまずいだろ。」
「でも....」
「部屋まで行けば思うぞんぶん鳴かせてやる。しかしここは駄目だ。」
グロイス王子は急に冷たくなって肌着とキルト服を投げつける。
プリセアの忘れかけた羞恥心を揺さぶってやろうという考えだ。
先に待っているぞ、と言い残して出ていってしまう。
高ぶった気持ちを抑えるように服を着直しながらプリセアはふと呟いた。
「死にたい....」
第13話 エミリナは再び捕らわれ、ジェローは屈する。
騎士ジェローはベランダで手紙を読んでいる。
何年も会っていない妹の字で家のことが書かれている。
年老いた母親、それから若い夫のことも。
そして最後に「帰ってきてほしい」と。
「ああ、それが出来ればな。」
しかし今のジェローは、ボルゴニアの王女でイビリア伯爵夫人のパガレアの家来の身。
家来というより操り人形のような状態だ。
政略結婚で退屈しているパガレアの言いなりになっているオモチャなのだ。
パガレアの夫であるイビリア伯フィトー・アンプラクは彼女には興味をしめさず、子供を作らないまま妻を三十六の歳にまでしてしまった。
権力のために王女を娶っておきながら、領地は甥っ子に継がせてアンプラク家の独立を守るという策略らしい。
まるで愛とは関係のない世界だ。
だからこそ妻のパガレアがジェローのような若い男を囲っていたり、あちこちの貴族と不倫をしていても文句を言わないのだろう。
ジェローは手紙の文面を何度も指先で撫でて妹のことを思った。
記憶から消えそうな面影を懸命に描き直そうとしているようだ。
そこへ別の騎士がやってくる。
慌てて手紙をポケットにしまう。
「パガレア様がお呼びだ。」
ジェローが女主人の部屋へ入ると、パガレアはたいそうな笑顔だった。
それを見て若い騎士は青くなってほとんどひれ伏すように膝をついた。
彼女がこういう笑顔をする時は怒っているときなのだ。
「可愛いお嬢さんがおいででしたわね。」
エミリナ姫のことだ。
パガレアはいつもベルを鳴らしてジェローを呼び出すので、彼の部屋にパガレアが来ることはめったに無い。
だから油断していた。
「それは....」
「いいえ、構わないわよ。ずいぶん疲れていたようだし、お前の部屋で休んでいたんでしょ。でも....もう元気になったから戻らせたわ。弟の所へね。」
弟というのはグロイス王子のことだ。
ジェローはがたがたと震える。
パガレアは彼の真ん前まで寄ってくると、伏せた頭に向かって嬉しそうに言った。
「お前も身軽になったことだし、いろいろ手伝ってもらうからね。」
「申しわけ....ございません....」
「弟の結婚祝いにけっこうなパーティを考えたの。結婚式の夜に....秘密のパーティよ。お前も参加するのよ。」
「私の責任です....」
消え入りそうなジェロー。
無視してパガレアは話し続ける。
「花嫁のつとめというのを可愛いプリセアに、義姉として教えてあげなくちゃね。」
「お許しください。」
「ジェロー! お前の主人は誰?」
「パガレア様....あなた一人です。」
女主人は満足そうにするとスカートをまくり上げる。
下着のない露わな赤い花にむかって騎士ジェローは服従の口付けをした。
ボルゴニアのグロイス王子とカヴァルナのプリセア姫の結婚まであと二日。
国中から、また諸外国から大勢の賓客や見物人が訪れ、首都モンボルクは蒸し風呂のような熱気に満ちた。
宿屋はどこも満室で、仕立屋や靴屋まで臨時の宿を提供する。
大工は空き地や市外に急ごしらえの小屋を建て、あぶれた路上の旅人に屋根だけはかけてやるというぐらいだ。
パレードのコースになっている道では全ての家が垂れ幕をさげ、窓辺に花を並べたりして準備に忙しい。
宮殿の中でも騒がしいのは同じだ。
キッチンには食材が天井にとどくぐらい積みあげられ、裏では家が十軒も建つほどの木材を大男たちが割って薪にしていた。
「鍋の数が足りないって?! あれほど多めに用意しろと言ったじゃないかね! マヌケ、トンマ、デクノボウ!」
大声でわめいているのは変態中年のボン・ペルツ。
今日ばかりは商人としての本業にいそしんでいるのだ。
頭をあんまり振り回すものだから帽子がつるっと落ちて、タコのように赤くなった禿頭が晒される。
帽子を拾ってくれた下男をにらみつけるようにして被り直すと、ペルツは酒倉役の所へ駆けていく。
「どうも男爵様、この度はまことにご出世おめでとうございます。いいえ、私めの口利きなんて全然たいした事じゃありません。....いえ、そんな....どうも、こんな物を頂いては....え、そうですか? ではでは....」
グロイス王子の腰巾着という立場を利用して、こうして何かと賄賂を受け取るのもペルツという男の商売の一つ。
「おいペルツ、儲かってるか?」
「いやぁ、ぼちぼちで、グラフコ様。」
ペルツは今貰ったばかりの金貨のいくらかをこの痩せた男に分ける。
グロイス王子の身辺を守る近衛隊長で、王子の古くからの悪友でもある。
家柄は悪くないくせに野蛮な性格で、十代の頃には王子とつるんで田舎の村を荒らしてまわり、ちょっとした騒ぎになった事もあるヤクザな男だ。
「おっ、そっちにおられるのはエミリナ様ですかね?」
「さすがペルツだな。分かるか。」
グラフコの後ろには一人の女が顔を隠して立っていた。
薄い布の袋をすっぽり頭に被って、体には粗末なコートをかけていた。足は裸足だ。
「....事情はお聞きしませんよ。ふひひ。」
ペルツに見送られながら、エミリナ姫はグラフコに連れられて北の塔へ歩いていった。
そこは死刑囚が閉じこめられる場所で、今はカヴァルナの兵士たちが数名いるはずだった。
「グロイス殿下も恐いおかただわい....。ま、こっちは仕事仕事。」
ペルツはまた拳をふりあげて召使いどもを叱りつけだした。
第14話 エミリナは捕虜になった祖国の兵士らに姦される。
二ヶ月前、カヴァルナ王国はボルゴニア軍に滅ぼされた。
プリセア姫とともに城の塔に最後までたてこもっていた兵士達は、プリセアの投降で命を救われる約束だった。
しかし残忍なグロイス王子がそんな約束を守るはずはなく、プリセアの知らない間に名のある騎士や精鋭部隊の兵士などは皆殺しになっていた。
そして、その内のわずか六人だけが捕虜としてボルゴニアに連行されていた。
何か使い道があるかと生き残らせておいたものらしい。
北の塔には地下牢があって死刑囚をしばらく放りこんでおく場所に決まっていた。
もちろん捕虜の六人はそんなことは知らないので、いつか助けられるだろうという希望を持っていた。
しかし監禁が何十日も続くうちに、まさかこのまま飼い殺しになるのかと不安になった。
地下牢は暗くて天井の穴から少し光が差しこむだけ。
その穴からは食料の入ったカゴが下ろされたり、糞尿を溜めた壺を引き上げてくれるだけ。
肩車をすれば届かないわけではないが、いつもは重い鉄格子で塞がれていた。
その天井の穴に今日は見慣れない顔が現れた。
「おい良かったな。そこから出してやるぞ。明日だ。」
「えっ、本当か! 出られるのか!」
牢屋生活で幽霊のようになった兵士達は急に生き生きとしだした。
しかし希望は儚かった。
「ああ、明日の朝に出してやる。そしてすぐに縛り首だ。」
グラフコは冷酷にそう言うと足もとの穴にむかって聞き耳を立てた。
暗闇の底はしばらくしんと静まっていたが、そのうち啜り泣く声が聞こえてきた。
どんなに勇敢な兵士でも悲惨な牢獄ですごせば根性も弱くなってしまうのだ。
「偉大なグロイス殿下はお前たちに最期の贈り物をしてやるとよ。受け取れ。」
しばらくして兵士達の頭上に白い足がぶらさがった。
それからゆっくり降りてきた。裸の少女だった。
彼女は足が地面につくと掴んでいたロープを放す。
それから両手を伸ばして周囲を探ろうとした。
頭には袋をかぶっている。
「きゃ!」
手に男の体が触れたとたん彼女は飛びのいた。
天井からまたグラフコの声がする。
「おい、人生最後の女だ。しっかり味わえよ。灯りもやるからな。」
火のついた松明が投げこまれ地下牢は明るくなる。
少女は壁のほうに寄って小さくなって震えていた。
男達は声をかける。
「お嬢さん、何もしないから安心しな。」
紳士的なふるまいをする気力がまだ残っていたのか、死の絶望が無気力にさせていたのか、裸の女を見ても彼らに獣欲が起こることはないらしい。それで少女は少し安堵したようだ。
「....ありがとうございます。」
少女は顔にかかっていた布をとり大事なところを隠そうとした。
それがまずかった。
その顔を見た瞬間、男達は驚いて立ちあがった。
「エ、エミリナ様っ!」
「お、お前達....どうして....」
ひざまづくことも忘れてカヴァルナの兵士達はプリセア姫の従妹の裸を見おろす。
エミリナも呆然となって胸を隠すのが精一杯。
「姫様、どういう....これはどうしたんですか?」
その時、男達の目に震えるエミリナのお尻が見えた。
そこには敵国ボルゴニアの紋章が赤黒く焼き印されていた。
(敵の女になったのか....じゃあプリセア様も....オレ達はもう用無しか!)
そう思ったとたん、見捨てられた家来たちの中で怒りと肉欲が一緒になって燃えあがった。
急に恐ろしい顔つきになって迫る六人の男。
その股間で肉の塊がむくむくと頭をもたげていく。
「お、お前達? あの....えっ、いや....いやっ、いやああああぁーっ!」
松明の揺れる灯りのなか、エミリナの小さな肢体にむかって無数の手が伸びた。
ケダモノと化した六人の男は生け贄の少女を土のうえに組みしき、暴れる細い手足を押さえつける。
「放してっ、放しなさぁい! いやああっ、許して! ....しないでえええーっ!」
泣き叫ぶエミリナの頼みも聞かず、初めの兵士が狼のような遠吠えとともに肉のカタマリを突きこむと、地下牢は止むことのない悲鳴で満たされた。
暗くて湿った地下牢での長い苦労のために、高潔なカヴァルナの兵士たちも心が荒んでしまったのだろう。
明日には死刑、そして目の前にはエミリナ姫の若い肉体。
自分たちの命と引きかえに敵の女になって生き延びようとする王族の裏切り。
それを考えると六人の捕虜たちは全身の血が沸騰しそうな怒りを感じた。
その怨念はそのまま獣の欲望になって、六人の股間で熱く滾るカタマリになっていた。
「ちくしょう、敵には....抱かれておいて....家来とは嫌かよ!」
乱暴に腰をうちつけて兵士が恨みごとを言う。
エミリナは泣きながらも必死に言い訳をしようとする。
「ち、違うの....うああっ! そんなこと、あ....ありませんっ。」
「ボルゴニアの犬どもに処女まで差し上げて、ブタみたいにお尻に焼き印されて、よくそんなことが言えるもんだな!」
「違うっ! 信じてっ、そんなの....違います! だって無理矢理....」
懇願するエミリナの青い瞳から涙がこぼれても、男達の信頼を得ることはできない。
「どうせ俺達は死刑なんだ! もう関係ないんだよ。」
「そうだ。エミリナ様....見苦しいですよ、今さら!」
兵士たちは口々に高貴な生まれの少女を罵った。
そして子羊を屠殺するときのように四肢を掴むと力まかせに引き伸ばす。
抵抗もむなしくエミリナの体は空中に浮かばせられ、姦している男のほうへ強引に押しつけられる。
男の肉槍が内臓をえぐる。
「嫌ですっ、もう嫌あぁ! 痛いのっ、ほんとに痛いからあぁ!」
そんな悲鳴も聞いてはもらえなかった。
やがて、いちばん若そうな兵士が暴れる彼女の金髪をつかんで、男根をエミリナの涙まみれの顔に押しつける。
二ヶ月も風呂に入っていない体からは人間とは思えないほどの異臭がした。
「ん....うぐっ、うええっ!」
「うわ、吐きやがった。そんなに臭いかよ。」
「この臭いのも....あ、あんた達のせいなんだ! その口でお詫びしてくださいよ。」
その青年はザクロの実を割るように両手で口をこじ開けると、まっ赤な喉へ肉棒をねじこむ。
「うぐっ....ん....ふーっ、ふーっ!」
辛そうに鼻息をたてる。まるで腐った肉のような凄まじい匂い。
そして酸っぱい気持ち悪い味。
目の前でうごめく男の体。
戦場でボルゴニアの兵士たちに陵辱されたときの記憶がよみがえる。
彼らは地面にカヴァルナの旗を広げ、その上でエミリナを輪姦した。
ひっぱたかれ、つねられ、笑いものにされた。
男の匂いと味を教えられ、胎内に精を注がれて妊娠の恐怖に怯えた。
その悪夢が再びおとずれたのだ。
「うあ、エミリナ様っ、エ....エミリナ様あーっ!」
捕虜たちはエミリナの上下の肉めがけて無遠慮に男根を突っこみながらも、そう姫君の名を繰り返し呼んでいた。
かつてプリセア姫が戦う姫君として敬愛されていたのに対し、従妹のエミリナ姫は愛くるしい深窓のお姫様として兵士達から慕われていた。
二人はカヴァルナ王国に咲く二輪のバラだった。
でもそんな思慕が強ければ強いほど、六人の男達は二人の裏切りを許せなかった。
「思い知れ! 誰のために戦ってきたんだよ!」
その言葉はエミリナにとって何よりも辛かった。
カヴァルナの王族に生まれたというだけの自分、それもまだ十四歳の少女に何ができたというのか。
なんの苦労も知らない平和な暮らしから一転して地獄のような目にあって、エミリナ姫は何を恨んでよいかも分からないで、捨てられた子猫のようにただ運命に怯えるばかりだった。
第15話 エミリナは祖国の男達に精を注がれる。
エミリナ姫の青い瞳には自分の口に押しこまれる醜い肉の塊がうつっていた。
男の欲望で固く張りきったカタマリは、太い杵が臼をつくようにエミリナの喉を乱暴に姦している。
「おううぅ....んぐっ! んぶうああっ、あぅ....ぐ....」
汗と尿が混じって発酵した強烈な男根の風味を少しでも薄めようとするのか、エミリナの口はたくさんの唾液を分泌する。
それは白い泡になって唇からあふれ出し、男の陰毛にからんでベチャベチャと下品な音をさせる。
情けのない家来たちの無礼過ぎるしうちに、エミリナ姫は敵に姦されたときとは別の屈辱を感じた。
そして絶望がこんなに人間を変えてしまうことが心の底から恐かった。
「あぐうっ! んあうう....ひい! んひいっ、うぶうああぁっ!」
エミリナの叫び声はもちろん痛みと恥ずかしさと恐怖から出たものだったけれど、兵士達には淫乱の証拠のように聞こえた。
彼らは憎しみがますほど興奮するのか、いよいよ激しく少女を姦し続ける。
細い肢体は関節がきしんで今にも外れそうだ。
「痛ぁ....うぐあっ、いっ....んうああっ! うあっ、痛いからあぁ! んぐぅ....」
「うおおっ! 出る....ひ、姫様ぁっ!」
若い兵士は急にそう呻くとエミリナの頭をわし掴みにして肉棒を付け根まで挿しこんだ。
たちまち男の腰はビクリと痙攣し、舌の上に乗っている固いモノも同じように跳ねた。
そして熱い男の精が喉の奥にむかって発射された。
「おぐううぅ....うう....」
「エミリナ....様、うあっ。」
兵士は腰を幼い主人の顔にぶつけるようにして最後まで出しつくす。
口が解放されたとたんエミリナは辛そうに咳こんで、息を詰まらせる粘液をこみあげる胃液とともに吐き出した。
しかしその様子がなおさら男達を逆上させたのだろうか。
彼らは同情のかけらもなく、また別の男が姫君の口に垢まみれの汚れた肉棒を突っこんだだけだった。
「うあっ、あぶぅ....あ、ゆ....許ひてえぇ!」
床のうえでは松明が燃えて人影を壁に映しだしている。
男女七人が一つに繋がってまるで黒い巨大な怪物のようだ。
七人の呻き声も牢屋じゅうに反響して、地獄の阿鼻叫喚そのもの。
エミリナ姫の目には揺れる炎を背にした捕虜の男達のどす黒い顔が、憎悪と絶望と情欲のまじった眼差しで取り囲んでいるのが見える。
明日には死刑という運命が彼らから人間らしさを奪っていた。
六人の手は彼女の全身を押さえつつ、あいた手を伸ばして白い首筋や膨らみかけた乳房、また度重なる陵辱のためにアザのついた太股などを撫で回してくる。
やがてエミリナの秘肉の中に挿されているモノが動きを激しくし始めた。
男はエミリナが聞きたくない言葉をいう。
「こっちも出る! くっ! で、出るっ!」
「そんな....うぐっ、んくああっ! だ....駄目、出しちゃ....んううっ!」
せめて外にという願いを言おうとした口を男根が塞ぐ。
肉棒の突撃はだんだん早くなり、男はエミリナのお腹のうえに涎を滴らせつつ、絶頂にむかって狂ったように突きまくった。
「うおおっ! 出るぞぉっ! うがああっ、エ....エミリナ様あーっ!」
「んぐううぁ....あぐ、うぐううううーっ!」
(いけない! 出しちゃ....中に出したら....駄目っ、抜いてえっ!)
心の中の叫びは通じず、男根はどくどくと脈をうって欲望の体液を噴出させた。
望まない精を胎内に注がれるおぞましさ。
六人もの男からいっせいに姦される屈辱に、エミリナ姫の肉体もまるで果汁を搾られるオレンジのように汗と涙、唾液と愛液、そして終いには小水まで漏らして、獣と化した男達のまえに潰れ果てた。
男達はひととおりエミリナを姦すと、あらゆる罪に汚れきった肉体を冷たい床に下ろした。
もうこれで人生にはやる事がないというふうに。
ぼろぼろになったエミリナは股間から流れでる白いものを見て呟く。
「....ひどいです。こんなの....赤ちゃんができたら....」
一人が答えた。
「孕んでくださいよ。」
皆が顔をもちあげる。消えかけた松明の灯りのなかで、男達はそれが唯一の救いであるかのように繰り返した。
「そうだ、孕めばいいんだ!」
「エミリナ様に孕んでもらおう! オレ達の子供だ!」
「いやあああーっ!」
たちまち死人のような体を起こすと六人はまたエミリナに襲いかかる。
痩せて幽霊のようになっているくせに疲れを知らないかのような猛烈な欲望だった。
「やめてええぇ....もう嫌ぁっ! どうしてなの? ひ....酷すぎるっ。」
だがその時エミリナは薄暗がりのうちにも、自分の上に覆いかぶさっている兵士達の鬼のような顔が涙に濡れているのに気付いた。
そう。
六人ともエミリナを姦しながら泣いていたのだ。
(お前達....)
昔あの従姉のプリセア姫が、戦死した兵の子供に「ごめんね」と泣いて謝っていたのを思い出した。
戦争は勝ちだったのにどうしてそんなに従姉は自分自身を責めているんだろう。
不思議に思ったものだ。
でも....これが国を治める王族の責任なのだ。
民に犠牲がでること、国が弱いことはそれだけで罪なのだ。
思わずエミリナもまたあの日のプリセアのように「ごめんなさい」と繰り返していた。
そして泣きながら兵士を抱きしめていた。
「ごめんね、ごめんなさい....ごめんなさい、ごめんなさいっ....」
「エミリナ様っ! うわああぁ、エミリナ様ぁーっ!」
男達はまた順番にエミリナを姦しては、衰えた体に残る命の種を尽きるまで注ぎこんだ。
やがて七人がみな疲れ果てて眠ってしまうまで涙の交わりは続いた。
第16話 プリセア姫はグロイス王子と結婚する
従妹のエミリナが祖国カヴァルナの男達の精を受けていたころ、プリセア姫の体には邪悪なボルゴニアのグロイス王子が精を注いでいた。
戦地から帰ってからというものグロイスは毎日に何度もプリセアを姦し、ありったけの子種で彼女の胎を満たした。
そこには何が何でも孕ませようという執念が感じられた。
ひょっとしたらそれは、やがて来る運命の予感だったのかも知れない。
目が覚めるともう朝も遅い時間。
グロイスはとっくにおらず皺くちゃのシーツと体液のシミが昨夜の情事のなごり。
浴室へむかったプリセアは昨夜の汗を洗い落とす。
体中につけられたキスの痕を召使いに見られても、慣れっこになっていてあまり恥ずかしくはない。
「もう....諦めなくては。」
カヴァルナの美しき戦う姫と呼ばれたプリセアも弱気になっていた。
兵を率いて戦場で剣をふるうのは得意でも、味方と争いあうような陰謀の世界は苦手なのだ。
なにより女として肉体を弄ばれ続けた二ヶ月が彼女を変えていた。
プリセアの中にもう一人の女がいて、人生を乗っ取ろうとしているような気がする。
「あ....」
自分の声に驚いてプリセアは我にかえる。
彼女の右手は知らないうちに乳房を愛撫していた。
(いけない、バカッ。)
あわてて体を湯に沈める。
でも湯の中で慰めをうばわれた乳房がじんじんと疼き、プリセアの手をまた動かさせようとする。
自分でやるよりもグロイス王子が来てくれれば....そんな望みさえ浮かぶ。
自己嫌悪だ。
部屋に戻ると、そこには花嫁のドレスが服掛けにかかって立っている。
明日これを着て挙式して、それでも自分は自分でいられるだろうか?
(しっかりしなくちゃ! みんなのために....お父様とお母様のためにも。)
カヴァルナ陥落の日、グロイス王子に殺された父の血塗れの首を思い出す。
するとプリセアの緩んだ心は再び引き締まる。
心が砕けてしまいそうになる度にプリセアはそうして自分の立場を再確認してきた。
それでも、まだたった二ヶ月しかたっていないのに、父親の姿は一日ごとにぼんやりとして、そのうちに思い出せなくなりそうだった。
(だって....ここは何もかも違いすぎる。)
カヴァルナのプリセア姫の中に生まれたもう一人、ボルゴニアのプリセアが花嫁衣装を着て立っている。
そんな気がした。
あのカヴァルナ陥落の日から二ヶ月。
プリセア姫はついにボルゴニアの王家シェレーン家の一員になった。
格式ばってめんどうな結婚の儀式を終えるとプリセア・ソフィニカ・シェレーンという名に変わり、正式にボルゴニア王国の太子妃として冠を受ける。
アルノス王の説明では、祖国のカヴァルナはプリセアの直轄地としてカヴァルナ王族の一人が代官になるという。
形の上ではカヴァルナは平和を手にしたように見える。
しかし税金や軍役や裁判などの権限はプリセアではなくアルノス王のものになるし、ボルゴニアの監視部隊も駐留するということで状態は占領となにも変わらない。
プリセアの帰郷さえ当分は許されそうになかった。
(焦ってはいけない。カヴァルナのために。)
プリセアはそう言い聞かせる。
パレードで民衆に笑顔を見せたのもそんな義務感からだった。
しかし、彼女が守ろうとしているカヴァルナの人々の一部が、前日に処刑されていたことはプリセアは知ることができなかった。
二ヶ月前のカヴァルナ陥落のさい、プリセア姫が投降することで命を救われたはずの精鋭兵たちが後日密かに殺され、その最後の六人も昨日こっそり縛り首になっていたことも、その前にエミリナが餌食になったこともだ。
「奥方。ほら、あやつらが北に住む異民族どもだ。初めて見るだろ。」
上半身を裸にして腰には毛皮を巻き、顔を黒く塗っている。
それを指差して花婿のグロイス王子は笑う。
「あれでも奴らはお洒落をしてきたつもりらしい。こういう野蛮な連中がボルゴニアの領土には山ほどいる。カヴァルナの洗練された文化で教育してほしいものだ。」(この人は皮肉を言っているんだわ。私がそんな傲慢なことは嫌いと知ってるのに。)
プリセアは黙って笑顔だけで答える。
これが今の彼女にできる戦い方なのかも知れない。
第17話 愛のパーティ。プリセア姫は浣腸をほどこされる。
王族の結婚ともなれば初夜だって儀式の一つ。
役人どもの前で形だけの床入りが済むと、やっと夫婦は解放される。
もっともプリセアは悪趣味なグロイス王子のことだから人前でいきなり姦しはじめるのではないかと気が気でなかった。
よほど疲れたのかグロイス王子はさっさとイビキをかいていた。
交わりもせずに眠るなんてこの男にしては珍しいことだ。
プリセアも横になる。
眠れそうにない....と思ったけれど、体のほうは睡眠を求めていたようだ。
どれくらい経っただろう。
プリセアは真夜中に揺り起こされた。
義姉のパガレアが来ていて「お祝いのパーティ」を用意したからと誘った。
彼女の本性を知らないプリセアはこんな深夜にパーティという不自然さにも何の疑いも持たないで、心からお礼を言った。
ふだん着に着替えるとグロイスと共にパガレアの部屋へ向かう。
だが部屋に入ったとたんプリセアの甘い考えはうち砕かれた。
パーティといいながら部屋にはそんな用意はされてなかった。
ただ飲み物が少し置かれているだけ。
そしてパガレアだけでなく騎士ジェローも待っていた。
プリセアは動揺したが、表情に出すのはどうにか堪えた。
パガレアが言う。
「今夜のは愛のパーティってところかしら? 世の中にはいろんな愛の形があるものね。可愛い義妹にはよく分かって欲しいわね。」
パガレアはそう話してからジェローの腰に手を回し、濃厚なキスをした。
「どういうことです!」
プリセアがグロイス王子のほうに振り向くと、グロイスは椅子に座っている少女をしめした。
「エ....ミリナ....」
プリセアの従妹は破れた服をまとって、体中を汚れまみれにして人形のように気を失っていた。
プリセアが駆け寄って声をかけても、切れた唇をちょっと動かしただけで目を覚まさない。
「何....を、あなた達! この子に何をしたの!」
グロイスはにやにやしているだけ。
プリセアにはやっと全部が罠だったことが分かった。
男の広い胸に掴みかかって罵った。
「悪魔! 騙したのね!」
「憎いか? もっと私を憎め。そうだ。それでこそ姦しがいがある。」
グロイス王子はパガレアとジェローの前でぞんぶんにプリセアに恥をかかせてやるつもりだった。
プリセアの心に芽生えていたジェローへのささやかな恋も、グロイスにとっては快楽を盛りあげる玩具に過ぎないのだ。
「壁に手をついて、ほら! 尻を出せ。」
プリセアは壁にかかったタペストリーに顔を押しつけられ、スカートをめくり上げられる。
ジェロー達にお尻をむけて下着まで脱がされ、恥ずかしい所を晒されている。
いっそ人間であることを忘れてしまいたくなる。
「いいか、動くなよ....」
「ひいっ!」
彼女が悲鳴をあげたのは予想していない部分を弄られたから。
グロイスは女の谷間の部分ではなく、小さく窄んだ後ろの穴にイタズラを仕掛けたのだ。
「な、何を入れて....駄目っ! あ....」
妙な冷たさ。首を向けて見ると、最初は指かと思っていたものは実は金属でできた道具の先端だった。
子供が遊ぶ水鉄砲のようなものを高貴な姫君のお尻の穴に突きさして、非情なグロイス王子はぶざまな花嫁のすがたをせせら笑う。
そして手をゆっくり動かすと、同時にプリセアの体に何かが流れこんでくる。
「ひっいぃ....いやぁ! うわあぁ、待って....待ってえぇ!」
「姫には体の中からすっかり綺麗になってもらおう。....おい、暴れるとケガをするぞ。」
「ひどいっ!」
(やっぱりこの人は私を人間だとは思ってないんだ。結婚した相手をこんなに辱めるなんて。)
生ぬるい水がじゅるじゅると音をたてて入ってくる。
お腹が膨らむのと反対に息が搾りだされてプリセアは喘ぎ苦しんだ。
「うああ....ん、うっ....はあっ....あぁ....」
初めて経験する不気味な感覚、耐えられない胸ぐるしさ。
体をよじって逃げようとは思っても、この道具がお尻から抜けたらたちまち汚いものが漏れてしまいそうな気がした。
「しないで! もう無理ですから....うぐっ!」
「もう少し....ほら、全部入ったぞ。おう、プリセア! まるで子を孕んだみたいじゃないか。」
「あら、ほんとにそんな感じね。それでも美しいのが、さすがプリセアね。」
グロイス王子とパガレア王女が姉弟でからかう。
それでもプリセアは恥ずかしがるどころではない。
浣腸器を抜かれる瞬間「ひっ」と小さく鳴いたあとは、歯をくいしばって脂汗を垂らすばかりだ。
グルグル....
プリセアの体は早くも、この理屈にあわない侵入物を吐き出そうとして盛んに腸を動かしはじめた。
でもその健全な反応が、彼女自身を苦しめる。
プリセアはスカートの前をしぼるように掴んで必死に堪えた。
「おトイレに....」
「行ってくるか? だいぶ遠いぞ。」
この部屋からは長い廊下を通っていかなくてはいけない。
とても保ちそうにない。
お尻を振りながらプリセアは「おまる」を探した。
貴族の寝室にはあっていいはず。
でも見あたらない。
焦るほどに便意が高まり、抑えようとするプリセアのお尻は筋肉が痙攣してくる。
「酷いっ! こんなの....あううっ....んっ、はあっ、ああうっ!」
体は心とは無関係にただ楽になろうとして排泄を求める。
そんな生理現象に従ってしまいたい気持ちが湧いてくる。
でも人前で排泄するなんて死ぬより辛い恥だ。
体と心の葛藤がプリセアに地獄のような苦しみをもたらした。
「いああぁ....許して....うっ、お許しください。お願いいぃ....」
(漏れてしまう。ジェローの目の前で....それだけは、ぜったい嫌。)
力を抜くと漏れそうだし力めば腹が締まってきつい。
詰まった水が出口を求めて体内で暴れているようだ。
プリセアはそのうちに喋ることも出来なくなって、ふっふっと短い息をついてはタペストリーを掻きむしった。
最後が近かった。
その時、パガレアが救いの言葉をかけた。
「大丈夫? そうそう、隣の部屋におまるを用意しておいたわ。良かったら使って。」
「うあぁ....」
急いで行こうとするとキュウッと迫る便意。
目眩がしてどこがドアなのかも分からなくなる。
見苦しく内股になってヨロヨロ歩いていく。
あと数歩だというのに恐ろしく遠い。
「漏らしたらまた入れるぞ。」
グロイス王子にそう言われてもプリセアには悔しく思う余裕もなかった。
第18話 プリセア姫は騎士ジェローの前で絶頂する。
プリセア姫がトイレを終えて出てきたとき、部屋にはパガレアの喘ぎ声が響いていた。
騎士のジェローはすっかり裸になって、ベッドを激しくきしませて女主人に肉の奉仕をしていた。
女のお尻に男の腰がぶつかってパンパンと鳴っているようすは、心をもった人間というよりはカラクリ人形のようでさえある。
「いいわ、もっとよっ! 激しくっ、し....しなさいっ、もっとおぉ!」
「はいっ、パガレア様っ!」
淫らに働くジェローの背中を見てプリセアは胸が詰まる気分だ。
信じていたのに裏切られたという悔しさだけでなく、彼の相手が自分でないことがなぜか切ない。
「綺麗にしてきたか?」
グロイス王子が後ろから花嫁の首筋を撫でる。
「はい。」
ご丁寧に、隣の部屋にはおまるだけでなくお尻を洗うお湯やたらいまで用意されていた。
しかもお腹に入れられたのもただのぬるま湯ではなくハーブを効かせた液体だった。
自分の排泄物が花や青葉の香りをさせておまるの中に落ちているのを見て、プリセアは自分を見失いそうになった。
こんなにも徹底した屈辱を受け続けたら、いつか彼女の心は麻痺しきって本当にグロイスの奴隷になってしまう、そんな気がしたのだ。
「もう服はいるまい。」
グロイスの両手が胸元に回って、薄い夏用の部屋着をいっきに引き裂いた。
こういう野蛮なことが好きな男なのだ。
そんな男とそれから死ぬまで付き合わねばならないのだ。
プリセアはジェローの逞しい背中を見ながら、グロイス王子の手で裸に剥かれていった。
パガレアは彼女の視線に気付いたらしく、ジェローに後ろを向くように指示する。
ジェローと目が合ってプリセアは顔をそむける。
「ねえ、ジェロー。プリセアって美しいわね。悪趣味な弟から毎日いやらしいことをされまくっているのに、全然うぶな処女みたいなんだからね。」
「はい、プリセア様は....美しいです。」
「じゃあ美しいプリセアが下品に堕ちていくのを、今夜はよく見てあげましょう。」
ベッドの二人は体位を変え、ゆっくり交わりを続けつつプリセア姫とグロイス王子を見物し始める。
「見ないで....」
プリセアは小さく呟いた。
グロイスの左右の手は彼女の大きな乳房を搾り、毛を剃られた下腹部をさぐって恥骨のあたりをくすぐる。
「あっ」と呻いてプリセアはのけ反り、大きく息を吐いてはぶるぶると肩を震わせる。
足が自然に開く。
恥ずかしさとは反対にジェローに見られたい気持ちがどこからか湧いてくる。
(裏切り者っ、裏切り者....)
心の中でそう罵ってはみてもジェローの端麗な顔立ちとプリセアと同じ青みがかった瞳が、彼女の中に住むもう一人の女を呼びさます。
(気持ちいいんでしょ。そう言ってしまいなさいよ。プライドなんか捨てて....姦して、姦してって言ってしまえばいいのよ。)
そして男の指が肉の谷間に及んだときプリセアの口は勝手に動いていた。
「あっ、そこぉ。」
いけない、と我に帰ってプリセアは唇を噛む。
でも遅かった。
グロイスは彼女の心が崩れ始めたのを逃さず、もっと指を沈めて女の扉の奥へ進入する。
「うああああああぁ....あっ....」
喉から快感の声が搾り出される。
それが始まりの合図だった。
もう抑えることはできなかった。
「あっ、うああ! はあんっ! あん、いやあっ....あくううぅ! だめええっ!」
「プリセア、はしたないぞ。遠慮しろ。」
男は冗談を言いつつも指を二本三本と押しこんで、熱く潤ってくる肉のヒダを擦りまくった。
「いや、いやぁ....くんっ! イクっ、うああぁん! イクううぅ....」
プリセアが悶えて頭を振ると栗色の髪が乱れて娼婦のように顔が半分隠れる。
涙の浮かんだ片目でジェローを見つめている彼女。
でも悲しみではない。
「みっ、見ないでっ! お願いぃ....あああっ、いくの....見ないでえええぇ! いやあっ!」
両手をグロイスの首筋に絡みつかせ、プリセアは言葉とは反対に腰をジェローのほうへ突き出すようにして絶頂の叫びをあげた。
「んくっ、きゃああんっ! あ....うあ、くうああああぁーっ!」
(ジェロー....見て。私....いやらしいの。見て....)
ぐっと突っ張った足がぶるっと震えて、やがてがくりと力が抜ける。
床に座りこみそうなプリセア姫の体をグロイス王子は支え、まだ快感の余波に喘いでいる淫靡な花嫁の姿をパガレアとジェローに見せつけた。
「どうかな、姉上。たった二ヶ月のうちによく飼い慣らしたものでしょう。」
「可愛いお嫁さんね。お父様に逆らってまで結婚したのも納得できるわ。」
「姉上がお誉めだぞ。プリセア、お礼を言わんか!」
「あり....がとう....ございます。」
かぼそく呟いているプリセアの薄く開いた目にはジェローだけが映っていた。
第19話 エミリナはグラフコ隊長のものにされる。
暗いところに何かがぶら下がっている。
少女は顔を覆っている手をおそるおそる下げる。
足だ。
痩せた男の足がぶら下がっているのだ。
がくん!
もう一人、もう一人、どんどん足が落ちてくる。
ぶらぶらと揺れる....
「きゃああああああっ!」
エミリナ姫は椅子から転げ落ちた。
さっきまで土だった床は柔らかいカーペットに変わっている。
でも少女はまだ夢を見ていたことに気付かないのか、床を泳ぐように這いずった。
人の足にぶつかる。
「ひいいぃ....」
「寝ぼけるな。プリセアに笑われるぞ。」
「やめてあげてっ。」
プリセアは男を押しのけると、傷だらけで震えている従妹を抱きしめた。
「しっかりして....ね、私が分かる?」
「いやぁっ! もう、しないで! だめえっ、殺さないでぇ!」
「エミリナっ!」
暴れていた少女はやがて落ち着きをとりもどす。
目の前にいるのが誰なのかもやっと分かったようだ。
「お従姉さま....わたし....ごめんなさい、わたし....」
「言わないで。ね、何も言わなくていいから....エミリナ。」
この従妹がどんな目に遭ってきたのかプリセアには聞かなくても分かる。
それは王女パガレアや騎士ジェローを善人だと信じてしまった自分の責任でもある。
でもここはボルゴニアなのだ。
カヴァルナを侵略した国の王宮なのだ。
ほかの誰が悪いのでもなく、プリセアの考えが甘すぎただけなのだ。
「許してね、エミリナ....私が悪いの。」
「湿っぽい話はそれぐらいにしてもらおうか。おい、グラフコ!」
ドアを開けて入ってきたのは肌の浅黒い野蛮なふんいきの男。
近衛隊長のグラフコだ。
「グラフコ、未来の従姉に挨拶しろ。プリセア、こいつはエミリナ姫のフィアンセだ。」
「なんですって!?」
その男のいやらしい視線に、プリセアは手で胸を隠す。
「こりゃあどうも、プリセア様のお裸を目にするのは久しぶりでございますな。」
カヴァルナの城で試合をさせられ兵士の前で裸に剥かれた、あの時のことを言っているのだ。
グラフコは無遠慮にじろじろと見下ろす。
「あいかわらずお美しい....おっ、でもお股のほうが涼しそうですなぁ。」
「こ、この人をどこかへやって!」
妻の頼みもグロイス王子は無視。
グラフコはしゃべり続ける。
「これからは家族づきあいさせて頂きたいものです。愛しのエミリナ様といっしょに。」
ひどい無礼さにプリセアは腹が立った。
だがグロイスは強引にエミリナを引っぱり上げると、こう言ってのけた。
「花嫁を受け取れ。」
グラフコ隊長はまるで品物のようにエミリナ姫を抱えると、プリセアが止めるのも聞かずに部屋をあとにする。
エミリナは驚くほど無抵抗のままで連れて行かれた。希望もなにもかも失った虚ろな目をして。
「プリセア、お前の仕事はこっちだ。」
「あの子を放してっ! もう酷いことさせないで。」
「余計なことを考えるな。」
「いや! んっ....」
グロイスはプリセアの唇を奪って舌を挿しいれる。
こうなると長いこと調教を施されたせいで、プリセアの体は男のいいなりになってしまう。
男の大きな舌で歯茎や口の天井を愛撫され、舌を絡められると脳天にまでピリピリと刺激が走る。
快感を与えられると他には何も考えられなくなるのだ。
「う....あおおぅ....んう....んっ。」
固く突っ張っていた体がふやけるように柔らかくなるのが見ていてもわかるらしく、パガレアが茶々を入れた。
「ねえ、ジェロー、本当はプリセアもただの女なのね。キスだけであんなに気持ちよさそうにしてるんだから。ほら、もっと私も気持ちよくさせなさい。」
「はい、パガレア様。」
騎士ジェローは女主人のお尻をぐんぐんと突き上げる。
彼女は弟夫婦に見せつけるように大声で悶えてみせる。
「ああん! そこっ、そこよ! ほらぁ....もっとしなさいっ! いいっ、凄いわあぁ!」
「パガレア様っ、パガレア様っ。」
ジェローが彼女の名を呼ぶのがプリセアの耳に痛い。
憎悪や嫉妬や無念さが頭の中でごちゃごちゃになってプリセアをどうでもいい気持ちにさせていく。
(考えたくない。もう悩むのは嫌! 姦して、わけが分からなくなるくらいに!)
グロイスの指が再び秘肉をえぐってくると彼女は自分から体を押しつける。
あふれた愛液が内股を滴っていくのが分かる。
(ごめんなさい、エミリナ....私、もう駄目になったみたい。許して。)
「んあ、あむ....ふうぁ....んうっ、んぁ、くうんっ....あふぅ。」
プリセアは両手をそっとグロイスの背に回すと、艶っぽい鼻息でグロイスの愛撫に反応しはじめた。
いっぽうパガレアを姦していた騎士ジェローは厳しい表情になってくる。
パガレアが察して尋ねる。
「ねえっ。お前、もうイキそうねぇ! あん、だらしないわねっ!」
「す、すみません! でも。」
「駄目よ、あぅ....ああんっ! な、中に出しちゃ駄目なの、分かってるわねっ!」
そんなことを言いながらもパガレアは足を回してジェローの腰を掴まえて放さない。
そして膣内のものを激しく締めあげる。
「いいわぁ、私も....はああん! 私もイキそうっ! もうちょっと頑張りなさい。」
「パガレアさまぁ、もう! お許しくだ....くださいっ!」
「駄目よ、まだだから! んはああぁ! まだ、イッちゃ駄目っ!」
「うぐっ、うわああああっ!」
ジェローは少年のような高い声で喚くと、いちかばちかというように乱暴に腰を使った。
「いいっ....ジェロー! すごぉい!」
「は、早くっ、パガレア様っ....」
ジェローの官能は限界を通りこし、もう精が漏れかけていた。
それでも奉仕の義務をつくそうと汗をまき散らして肉の突進を続けた。
そんな健気な努力にパガレアの体もますます熱く高ぶった。
「んくっ! あああんっ、ひあっ! イク....私もイクわあぁ!」
「で....出ますっ! パガレアさまああぁ!」
「出してっ! ジェロー、いっぱい出してぇ! 私っ....イクううううーっ!」
「うわああああっ!」
二人はいっしょにオーガズムを叫んだ。
ジェローが全身を震わせてパガレアの中に射精しているのを、グロイスに愛撫されながらプリセアは羨ましそうに見ていた。
第20話 プリセア姫はジェローの前でグロイスに姦される。
「今度はそっちの番よ。」
色っぽい汗にまみれた姉の命令をうけてグロイス王子は花嫁プリセア姫をベッドに運ぶ。
パガレアと騎士ジェローは立ちあがり、ベッドの主が入れ替わる。
「プリセア、四つん這いになれ。」
彼女の秘部はとっくに濡れきっている。
二重になった赤い肉のヒダが男に侵略されるのを待ちわびてヒクヒクと蠢いている。
そこをグロイスは男根の先で突っつく。
「あああぁ....」
入ろうとして入ってこない。
そんなイジワルがもどかしかった。
お尻を突き出すようにして男を求めるプリセア。
「なんだ? そんなに入れて欲しいのか? なら、はっきり言ったらいいだろ。」
「く....ください。」
「もっと、はっきり言え! 何が欲しいんだ!」
「グロイス様の....それを....」
義姉のパガレアが淫らな親切をする。
「プリセア、ちゃんと言いなさい。グロイス様の大きなおちんちんが欲しい、でしょ。」
「グ....ロイスさまの、大きな....お、おちんちんが....」
「突っこんで欲しいんだろ?」
「くださいっ! つ、突っこんでっ....おちんちん突っこんでえっ!」
「そら、味わえ!」
「んああああああぁーっ!」
ずぶりと貫いてくる刹那、プリセア姫はあられもない声で喜んだ。
「ひいんっ! ふうっ....んあ、うあああっ! きゃうっ! くああああん!」
シーツを握りしめて鳴きまくる。
ふと目を開けるとジェローの顔が飛びこんでくる。
肉欲の奴隷になった姫君を哀れむような眼差し。
「プリセア様....」
「ジェ....ジェロー、見ないでえぇ!」
ジェローのすぐ前で動物のように背後から姦されて乱れまくっている。
でも、みじめさが逆に快感を助長してしまう。
(もっと見て。もっと姦して。私を駄目にしてっ!)
「ひああっ! すごいの、あうう! あん、あん....こんなぁ、ひっ! ふああああっ!」
普段にない悶えようにグロイスも感心した。
「プリセア、えらく嬉しそうだな? 見られるのが気持ちいいのか?」
「そんな....きゃあああんっ! はいっ、そ....そうですぅ、見られて....んううぁ!」
グロイス王子はいよいよしつこく責める。
体を右に左にとねじりながら女の内壁の敏感なところを次々に探りだしていく。
「もう、んあああぁ....グロイス様っ、きゃああんっ! 駄目ええぇ....」
「はははは、またイキそうだな? そうだろ淫乱なお姫様っ?」
「い....言わないで、うあっ!」
プリセアの体を知りつくしたグロイスの言う通り、彼女はもうオーガズムの崖っぷちにきていた。
男根の一突きごとにビリビリと雷に打たれるような快感が背筋を走る。
「くうんっ、イクっ! ん....ふううっ! きゃあああん! イ、イクッ....」
「駄目だ。」
言葉とともに、ずるりと肉棒が抜かれる。
「う、あぅ....?」
もう少しというところで急におあずけをくったので、プリセアは潤んだ瞳で口惜しそうに相手のほうへ振り返った。
だがグロイスは大きな手を伸ばすと乱暴に彼女の上半身をベッドへ押しつけた。
そして....
「え? ちょっと、駄目です。うあああっ! へ、変なこと....しないでぇ!」
プリセアはうろたえた。
男の指がお尻の穴に侵入してきたものだから、また浣腸されるのかと怯えたのだ。
しかしグロイスの淫らな企みはもっと変態的だった。
「そこ違うっ....あ、違いますっ! そこは、そんな所....ちょっと待って!」
「姫もあんがい鈍いな。何のためにわざわざ浣腸したと思ってるんだ。」
「うあぁ!」
グロイスという男は股間に屹立する肉棒の先を、こともあろうに後ろの穴に押し当ててきたのだ。
「変です。そんなのっ....」
「慣れればどうってことないぞ。」
「そんなっ無理....無理いっ! だめ....こんなの....あ、いぁ....嫌あああああぁ!」
たっぷり愛液で濡れたグロイスの男根は押されるままにプリセアのアヌスにめりこんでくる。
「あ....ひいいぃ....」
「おお、入る入る。初めてにしてはうまいもんだ。誉めてやるぞ。」
「ひどい....あ....はあっ、はぅ....うあああっ!」
ついに男根の半分ほどがずっぷりと直腸の中に納まった。
グロイスはプリセアの後ろの穴が初体験に慣れるのを見計らうと、性器同士での交わりのような抜き差しをし始める。
プリセアは哀願した。
「いやぁ....と、止めてっ! 気持ちわるいぃ....止めてえぇ....」
「ほほう、お尻のほうもなかなかだぞ。」
「んくうぅ....無理です....も、もう無理っ! ひい、うああああっ....ああぁ....」
満たされない前の肉の痺れがお尻に伝わってプリセアにわけの分からない奇妙な感覚を引きおこす。
「変ですっ! こんな....うああっ! 苦しい、苦しいですっ! ふあああぁっ!」
「苦しいと言うくせに、前がどろどろに濡れてるな。どうしてだ?」
グロイスの指が秘部の奥に分け入って、白く濁った愛液を遊ぶように掻き出す。
腸の男根と膣の指がぶつかるたびにプリセアは失神しそうになる。
こんなふうに二つの器官をいっぺんに弄られる虐待にはとても耐えられなかった。
「駄目、ひどいっ! んくうっ....ひぃ....ひどおおおいぃっ!」
「そんなに前が寂しいなら、もう一本くれてやってもいいぞ。なあ、ジェロー。」
その言葉にプリセアはぎょっとした。
第21話 プリセア姫は二人がかりで前後から姦される。
「ジェロー、こいつをお使い。」
「まさか....いや、いやああああぁ!」
パガレアが騎士ジェローに渡したのは革製のペニス鞘だった。
船乗りがそういうものを使うという話はプリセアも聞いたことはあったけど、実物を目にしたのは初めてだ。
それにしても形がすさまじい。
本当のペニスとは似ても似つかない姿。
先端から根元までいくつも段々になっていて巨大な芋虫のような醜い姿だった。
パガレアが高笑いして種明かしをする。
「可愛い義妹のために作らせたの。特注品よ。」
「喜べ。いいプレゼントじゃないか。」
プリセア姫のお尻の穴を貫いているグロイス王子がからかった。
騎士ジェローは無表情のまま、その怪物みたいなペニス鞘を自分のそそり立った肉棒にかぶせてヒモを結ぶと、油のようなものをヌルヌルと塗っていく。
そして作業が終わるとゆっくりとベッドに歩み寄ってくる。
「そんなの嫌あぁ! ひっ、あぅ....あああん! こ、来ないでぇっ!」
「やっぱりプリセア様も生のほうがお好きなのですね。でも私の子種で孕ませてはいけませんから。」
魂のない瞳のままで口元だけにっこり笑うジェローが、プリセアには怖ろしかった。
金髪と端正な顔立ちがなおさら機械のような冷酷さを持っているようにさえ見えた。
「駄目っ、そんなの入れないで....しないでええぇ!」
「最初はちょっと慣れないかも知れませんが、大丈夫、この油にはポルガが混ぜてありますので。」
「あの薬? ....やめてっ。ダメ、もうあれは....あれは嫌あああぁっ!」
ポルガと聞いてプリセアはうろたえた。
薬がもたらす悦楽の地獄をまた味わわされてしまうのか。
でもどんなに足をばたつかせてもアヌスを貫かれた状態では逃げられない。
グロイスが笑う。
「おいおい、そんなに動くな。たまらんぞ。」
「入れないで。死んじゃう! ジェロー....やめなさいっ、許さないからあぁ!」
温もりのない革の棒がプリセア姫の女の扉に触れ、一気に突き刺さった。
「きゃああああああぁーっ!」
処女を失ったときのような凄まじい衝撃。
人間のものではない残酷な形がプリセアの膣を蹂躙する。
痛みと快楽が一塊になって彼女を打ちのめし、プリセアはだらしくなく失禁していた。
パガレアが呆れる。
「ジェローったら手加減を知らないんだから。プリセアが可哀想でしょう。」
「はい、申しわけありません。」
グロイスが無慈悲なことを命じる。
「構わないから動いてやれ。」
「ひ、だめ....もうしないでぇ....嫌だってばぁ! んああああーっ!」
プリセアが喚くのも聞こえないかのようにジェローは腰をゆっくり引いていく。
巨大な芋虫がずるずると姿を現す。
そしてまた突っこむ。
「いあああああぁーっ! ....あくうぅ....ひいいいいああっ!」
「プリセア、嬉しいだろ。姉上に感謝しろ! ジェロー、もっと動け!」
「ダメダメえーっ! 死んじゃうからっ、ジェロー! お願い、止めてええええっ!」
若い騎士の体は容赦なくカヴァルナの姫君を責め続ける。
だんだん早く、早くなっていく。
そしてグロイス王子もアヌスを貫く男根を無造作に動かしはじめる。
二人がかりでプリセアを殺そうとでもするようだった。
「きゃあああんっ、いやあああーっ! 止めてええーっ、ああくぅ....ひいいいいっ!」
「プリセアっ、狂ってしまえっ! 狂えっ!」
「んぐううぁ....ひっ、はああぅ、ひいぃっ! う....んあああくうぅ! あうっ!」
ブシュッブシュッと激しい音をさせて二本の男根がプリセアをえぐる。
愛液がとめどもなく流れてシーツをべっとりと汚す。
媚薬ポルガがもう回ってきたのか彼女は目眩をおぼえた。
それとともに全身がバラバラになりそうな強い官能が湧きあがってきた。
「ひあああーっ! イクのっ、うあああっ! もうっ、イクうううーっ!」
ビクン、と震えてプリセアの意識は落ちる。
だが失神したとたんにまた快感に叩き起こされる。
立て続けにオーガズムが襲ってきて神経が焼き切れそうだ。
「イクっ....だめええぇ! イクっ、もういやっ、だめなのおおぉ....きゃあああああんっ!」
プリセアが頭をふるたびに涙が飛び散る。
嬉し涙だ。
カヴァルナのプリセア姫は二人の男に前後から姦されながら、悶死しそうな快楽の地獄の中で喜びに泣きじゃくっていた。
「....プリセアったら、あんなに乱れて。凄いわ。」
パガレアはうっとりと眺めながら、高ぶってしまった体を自分で慰める。
あんなに激しく狂わせられるなんて女として羨ましいと思った。
やがて長かった悦楽の時間は最後にさしかかる。
「プリセアっ、うおっ! 出るぞ、尻の中に出してやるぞっ!」
グロイス王子はそう雄叫びをあげるとプリセアの肩を掴み、全身の力をこめてめちゃくちゃに突きあげた。
同時にジェローもまたプリセアの足を肩に担ぎあげて腰をぶつけまくった。
「プリセアさまぁーっ!」
「いあああぁ、死んじゃうぅっ! 恐いっ....イクうっ、イクううううぅっ! だめえええーっ! うぁ....うあああああああぁーっ!」
三人の体はベッドの上で壊れんばかりに大きく痙攣すると、絶頂が去るのを惜しむように何度も絡み悶えながらゆっくりと崩れた。
そしてしばらく繋がったまま動こうとはしなかった。
夜はすぐに明けた。
女主人を起こしに来た召使いの娘は、卑猥な体液にまみれてベッドに横たわる四人の男女を見て慌てて逃げていった。
第22話 ボルゴニアは反乱で滅び、カヴァルナ王国は復活する。
「反乱です!」
穏やかな朝を騒がせるその言葉はアルノス王を驚かせはしなかった。
反乱はいつもどおり潰せばいいだけのこと。
しかし広間に担ぎこまれてきた血塗れの兵士の口から「オランチアが....」と出たとたん、王はまっ青になって髭を揺らして怒鳴る。
「オランチアだと! まさか!」
それは西にある古くからの服属国だった。
大きな港があってボルゴニア王国にとって重要な収入源になっていた。
王はあわててオランチア侯爵を探させるが、既にこっそり首都モンボルクから脱出したあとだった。
昨日の結婚式が終わってすぐ逃げたのだ。
「グロイス、捕虜はいらんぞ! あの家を根絶やしにしろ!」
父の命令を待つまでもなくグロイス王子は精鋭軍を集めると、揃った部隊から先に率いて出撃していった。
銀色の川のようになって西へ流れていく軍隊の迫力は、そのままボルゴニア王国の怒りの強さだった。
結婚式に参列するために来ていた貴族たちも、競うように自分の護衛兵を差し出す。
だが我も我もと声をあげる中で、王女パガレアの夫でイビリア領のフィトー伯爵だけは違っていた。
「恥ずかしいことで、うちの兵は軽い装備しかして来なかったのです。残念ですが一緒に出兵はできかねます。」
「準備の悪いこと!」
夫のメンツもお構いなしにパガレアは皆の前でそう捨てゼリフをすると、怒って部屋へ去っていく。
フィトー伯爵は深々と頭をさげる。
「では、イビリアの兵士には都を守っていただこう。」
アルノス王は娘のわがままを償うように、そう命令して婿の名誉を救った。
それがフィトー伯爵のしかけた罠とも知らないで。
戦争になれたボルゴニアの行動は早い。
さらに翌日になると軍はほとんど出払ってしまった。
だがそうして首都が手薄になったのを幸いに、突然イビリア軍が寝返った。
結婚式から突然の出兵で混乱していた隙を突かれた首都モンボルクは、たいした抵抗もできずにわずか半日で制圧されてしまった。
「こんな事になるとは....わが国が....」
中庭で捕らえられたアルノス王の前にフィトー伯爵が立つ。
今朝まで家来だった男が今は自分をひざまづかせている。
人の前に屈する恥辱はもう何十年も味わったことがないだけに、アルノス王にはいっそう辛かった。
「王よ、あなたの政治は民を苦しめること多く、国を幸せにしませんでした。理由なき戦争を頻繁に起こし、最も必要なはずの平和をないがしろにしました。」
「決まり文句はいい。早くしてくれ。」
フィトーは剣を抜き、高く構える。
最後に王は小声で尋ねた。
「パガレアは....」
「もうお先に。」
あっけない一つの動作で偉大な王の首は落とされた。
反乱の騒ぎの中、プリセア姫は騎士ジェローに連れられて王宮の塔に立て籠もった。
彼はボルゴニアの兵士達をかき分けて上へ導く。
すると最上階の部屋にはカヴァルナの女達が集められていた。
従妹のエミリナもいた。
「姫様っ!」
懐かしい顔が群になってプリセアを取り囲む。
みんな酷い目に遭わされてきたのだろう。
顔にアザがある者、腕に包帯を巻いている娘や髪を短く切られた娘もいる。
また死んでしまった者の名を告げたりもする。
「ごめんなさい。私を許してね。」
プリセアがひまざづこうとすると女達も同じく伏せる。
彼女らがそうやって泣いたり抱き合ったりしている間に、騎士のジェローは扉を閉ざして閂をかけていた。
一緒にいたボルゴニアの兵士が不思議そうに聞く。
「何やってるんですか?」
「いいから、お前も上へ行け。」
男は言われるままに梯子をつたって塔の屋上へあがる。
見張りを含めて三人だ。
ふいに室内のプリセア達は上から悲鳴がするのに驚いた。
プリセアが慎重に梯子をあがるとボルゴニア兵が血溜まりに倒れていた。
「これ....あなたが?」
ジェローは何も答えないで兵士の剣を拾って渡すと、梯子を下りた。
プリセアは追う。
「どうして? あなたはパガレアの家来でしょう?」
「誰があんな女のっ! ....人にはいろいろ....事情があるんですよ。」
じっと扉のほうを見ているジェローの横顔には怒りと悲しみが読みとれた。
「そんなことよりプリセア様、この場を生き残ることが先です。」
ドン!ドン!
扉が打ち叩かれる。
向こうから大勢の兵士たちが扉を開けようとしていた。
「開けてくれ! 敵がそこまで来てるんだ!」
反乱軍が塔に押しいって来たらしい。
ボルゴニア兵も自分たちが生き残るために、この最上階へ上がりたいのだ。
しかしジェローは動かない。扉の向こうの声はだんだん殺気だってくる。
「開けろ! ふざけるな、てめえら、ここを開けやがれぇ!」
でもここで彼らを入れれば、逆上した彼らは見境なく捕虜の女達を殺してしまうかも知れないし、そうでなくともボルゴニア兵と一緒くたに混じっていれば攻めてくる反乱軍に皆殺しにされてしまうだろう。
プリセアにも分かった。
戦闘が終わるまでは絶対にここへ兵を入れてはいけないのだ。
扉を鳴らす音が変わった。
ボルゴニア兵は斧で破りにかかっている。
「みんな、屋上へ上がって! 私たちが防ぎます!」
プリセアがそう言うと女達が金切り声で止める。
「姫様ぁ、いけません!」
「お願いです! プリセア様、ご一緒にっ!」
扉はもう破られそうだ。
ぐずぐずしている時間はない。
「これは命令ですっ! 上がりなさい! ....ね、エミリナをお願い。」
プリセアの嘆願にやっと納得して女達は屋上へあがる。
ぐったりしているエミリナも皆で引っぱりあげる。
泣いてるカヴァルナの娘達を笑顔をつくって見届けたプリセアは、剣を抜いて鞘をほうり捨てると一太刀で梯子を斬り壊した。
そしてジェローの横に並ぶ。
「プリセア様、二人で戦いましょう。半時も持ちこたえれば逆にやつらが反乱軍に降参します。それまで絶対に生き残るんです!」
「ええ!」
二人の戦士が剣をかまえた時、大きな斧の一撃で扉が砕け散り、手負いのボルゴニア兵がどっとなだれこんできた。
グロイス王子戦死の知らせが伝わったのは首都陥落から十日後だった。
ボルゴニア軍は反乱軍と裏切った貴族の軍に挟まれて敗走し、王子は自刃して生を終えたという。
そして二ヶ月もすると各地に飛び火した戦闘も治まった。
ボルゴニアという大国は消えてしまい、首都モンボルクも復活したイビリア王国の領土の一部になった。
かつて支配されていた国々もほとんどが独立し、その中にはカヴァルナ王国もあった。
国を取り戻したプリセア姫は若い女王として王座についたが、いろいろな縁談を断り続けて生涯独身で通した。
その後の王位は、従妹のエミリナが生んだ男子に受け継がれた。
その子の父親については戦死したカヴァルナの名門貴族の男と一般には説明された。
しかし世間では実はプリセアの子ではないかという噂も流れたらしい。
といっても当のエミリナは心を病んでいたので、誰にも確かめようはない。
またプリセア女王が何故そうしたのかも誰にも分からない。
ただ....プリセアの側にはいつも一人の騎士の姿があったという。
余談。
あの戦争の後、商人ボン・ペルツの姿を見た者はない。
代わってモナという名の女商人がモンボルクの町で活躍したそうだ。